■源義経=ジンギスカン伝説
判官贔屓というが、日本人は弱く悲劇を伴う話に心惹かれる人種のようで、昔から人情話には思わず涙が出てしまう人が私も含め多いという…。確かに源義経 ほど、気の毒な役割を演じさせられた武将も歴史上あまり見当たらないのも事実で、母の常盤御前は敵将の平清盛の妾にされ、自分は寺に預けられる…。そうし てようやく巡り合った兄には拒絶されて…な訳で散々ですわ…。 あれだけ華々しい戦果をあげたにもかかわらず、鵯越の逆落としも、壇ノ浦の八艘飛びも、兄に 嫉妬された挙句、追い詰められて殺される…。哀れすぎますよね…。私も兄の頼朝より義経のほうが数段好きですもん。今も昔も私達はこの手の愛憎劇が大好き のようで、ある意味義経の生涯は日本人の嗜好のために作られたのだ!という研究者も多いのだが…。
結局、衣川で戦死するのがあまりにも気の毒だったのかは解りませんが、皆さんもご存知のように、義経には不死伝説が多い。代表的なものとして、1:北海道 に渡って先住民族の仲間になった。2:大陸に渡ってジンギスカンになった。という説がある。1:の説は私達が住む北海道に義経ゆかりの土地けっこうありますよ ね。
平泉のある岩手県から北海道にかけて本当に多いんですよ。まず、岩手県江刺市の岩谷堂。衣川の館から、火事に紛れて逃げのびた義経が、ここで配下を待 ち受けたと言われている。次に、青森県三厩町にある鞍馬山義経寺。ここにある厩石の上で、義経が無事に蝦夷に渡れるよう神に祈ったところ、三頭の龍馬が天 から与えられたという場所。そして義経は龍馬に乗って海を渡ったらしい…。蝦夷地最初の到着地、松前には義経石があって、義経がここで休息し、無事の渡海 を神に感謝した所だそうだ。この周辺にはご存知の方も多いと思うが、弁慶岬、義経山等、義経主従の名前をつけた場所が多い。蝦夷に渡った義経は、アイヌの 人々に助けられ、持ち前の勇気とカリスマ性で次第にその地において英雄になっていく。アイヌの娘との恋物語も多くあり、積丹岬では、義経に恋をして叶わな かったアイヌの娘が悲しみのあまり岩になってしまったという「メノコ岩」もある。
義経のこうした伝説の背景にはアイヌの神で、小柄ですばしっこく賢いオキ クルミ神と、大柄で力持ちのサマイクル神というコンビの存在があるらしい…。これが義経・弁慶に似ているから、この神たちの神話がいつの間にか義経生存の 伝説におきかえられた例が多く見られる。また、江戸時代に本州から蝦夷地に進出した者たちが、先住民族であるアイヌたちを同化・懐柔するために義経伝説を 積極的に流布させたという事実もある…。ただ、義経の一行の死を誰も確認はしていないというのも歴史上の事実であって、逃げ延びて北海道に渡ったのだ!と いうのも否定できないところもあるようなのね。それどころか、モンゴルに渡ってジンギスカンになった!って確かに私から言わせるとオイオイ…なんだけど。
ジンギスカンの話に戻るけど、その生い立ちなどに謎がひじょうに多い。1150年に生まれた事、父の名がエスガイといわれる事以外、解っていることがあ まりない。モンゴルの小国から挙兵し、大モンゴル帝国を打ち立てたのが1206年。義経が死んだとされるのは1189年で、年代的には問題ない。まして、 ジンギスカンと義経の間には、偶然とはいいきれない数々の共通点がある。
まず、モンゴル人の特性が、馬術に長けている事。義経も鵯越の逸話で知られるように、乗馬の名手である。ジンギスカン自身も合戦の体験に、鵯越に酷似した 場面があるという…。ジンギスカンがモンゴル帝国の初代皇帝として即位した時、9つの白旗を掲げたらしいのだが、白旗は源氏の旗印であり、9という数字 は、義経の名である九郎に通じる。また、ジンギスカンは酒を嗜まなかったようなのだが、義経もまったくの下戸で有名である。モンゴル人が日本の緑茶に似た ものを愛飲するのも、ジンギスカンにはじまったようだ…。
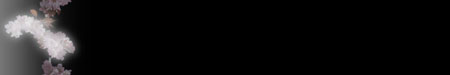
後にフビライが元寇を日本に向けたのは、祖父であるジンギスカンの日本への複雑な思いを代弁してのかたき討ち的行動だったのだ!と解釈する研究家も多い のね…。
確かに面白いけど、スケールでかくない?と思うのは私だけだろうか?皆さんはどう思われますかね…?
