■百足
幸いに、北海道ならまず見る事ないですけど、かなり苦手なのは、私だけじゃないですよね?ムカデは、背中が黒光りしていて、平たくて長い身体には多くの足があり、その足は赤や黄色でクネクネと這い進む姿が気持ち悪いですよね…。まして、アゴに毒を持っているらしく、咬まれると痺れるように痛く、何日も腫れが引かないそうです。
そういう嫌われる要素が、逆にムカデの神秘性を生んでいるのか、霊力にもつながっているみたいで、古くからムカデは、鉱山・鉱脈をつかさどる神の使いとされて来ました。
その理由なんですが、ムカデの形態が、鉱脈を掘り進む坑道の形に似ている事から、鉱山労働者の守り神とされるようになったんだと…。これが後に、金属加工や鍛冶屋の守り神として信仰へと広がったそうで…。

埼玉県秩父市の聖神社の社伝によると、元明天皇の慶雲五年(708)に、武蔵国秩父郡(現在の埼玉県秩父地方)で自然銅が発見されたとあり、献上された朝廷は喜んで、年号を和銅と改元し、日本最初の流通貨幣「和同開珎」を発行したそうです。その際、この地に鉱山の神であるカナヤマヒコ神を祀り、同時に元明天皇から雌雄一対の銅製のムカデが下賜されたと伝えられています。
ムカデは、毘沙門天(多聞天)の使いとしても知られていて、七福神の一人としても知られている毘沙門天は、元々仏法の守護神で、戦の神とされ、その像は鎧を纏っています。身体の節(体節)ごとに一対の足を持つムカデの形態が、鎧を着ているようにも見える事から、神使いとされた?のではないか?また、毘沙門天といえば、戦国時代、上杉謙信をはじめとして戦勝祈願の軍神として、多くの武将たちが信仰した事で知られていて、その神使いであるムカデも、戦国武将たちは、好んで兜や武具や旗差物等のデザインに取り入れていますしね…。
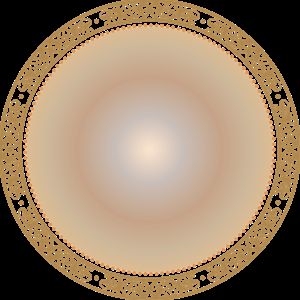
ムカデを神使いとする神社の御利益は、金運と開運とされる事が多く今日では、宝クジファンのパワースポットにもなっているそうで…。ムカデを神使いとしている神社は
聖神社(埼玉県秩父市)、戸河神社合祀・百足山神社(新潟県佐渡市)、白山神社(神奈川県鎌倉市)、白髭神社(埼玉県日高市)、巨椋神社(福井県敦賀市)等です。
