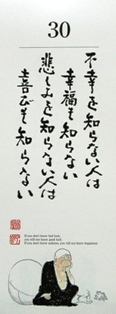■台湾グルメ旅行(おまけ)
(2015年12月29日) 台湾旅行中に気の付いたことや、疑問に感じたことを書き記してみた。
私達の滞在中は冬なのに、67年振りという30度を越す暑さで参った。
私は半そでシャツで汗をかいているのに、台北の女性はダウン・ジャケットを着ている人が多い。お洒落のつもりか、寒がり屋なのか不明だが、相当の我慢が必要なはずだ。

台湾ではホテルやレストランのトイレでは、紙を流してはいけないことになっている。
便器の脇に籠が置かれていて、そこに使用済みの紙を捨てる。
その籠が捨てた紙で溢れている時には、清潔好きの日本人なら相当に違和感を感じる。

日本のカキ氷と違い、氷は生ジュースを凍らせて、それを綿アメのようにフワフワに削ってある。今年の夏は日本でも大流行するに違いない。
トイレの紙に関しては、ベトナムでさえもそんなことは無かった。
なぜなんだろう?
もしかしたら下水道などのインフラが、急速な西洋化に追い付いていないのかもしれない。
私達の泊まったホテル・オークラはウォッシュレットで、紙も流しても良かったが、他のホテルじゃなくて良かったなー。

トイレの話題でもう1つ。
三越デパートの、男子便器の前に書かれた注意書きに納得した。
「向前一歩告 滴水不外落」は日本でも良く見かける標語だ。
これは分り易い。「一歩前へ。便器の外に漏らすな!」であろう。

中国語の漢字から、意味を推察するのも面白かった。
地下鉄の駅で、「小心月台間隙」とあった。
これは次のような意味だろう。
「小心」・・「注意」、「月台」・・「ホーム」、「間隙」・・「隙間」。「ホームと電車の間に隙間があるので、注意して下さい」。

私は「国が豊かになれば、バイクは無くなる」と思っていたが、そうではないようだ。
ベトナムのバイクの洪水を見慣れた私は、いつも日本語学校の生徒達に「ベトナムも豊かになれば、バイクから自動車になる。あなた達も車に乗れるようになるから、頑張りなさい」と言って来たが、今回の台北のバイクの氾濫を見ると、その予言は怪しくなった。

台湾の商店街には必ず屋根がある。
これは日本統治時代に、熱帯の夕立から逃げるために日本が台湾に導入させた方式である。
しかし、歩道の上は建物になっている。
土地の権利関係はどうなっているのだろうか?
歩道では勝手に屋台を出して商売をやっている人がいるところを見ると、歩道は道路なのかもしれない。そうなると、建物の所有者が2階以上を不法占拠をしているのだろうか?

(おまけの話)
ホテルで日本のニュースを知るために、NHKの衛星放送を見ていた。
ニュースが終ると、他のチャンネルに切り替える。
主に地元のテレビ局の番組を見た。

「見た」と言っても、「分って見ている」という意味ではない。
台湾は本省人は福建語を話す。
本省人とは日本統治時代以前から台湾に住んでいた人達のことを言う。
第二次世界大戦後の大陸の覇権を巡り、毛沢東に敗れて大陸から蒋介石と一緒に逃げて来たのが、外省人と言われていて、北京語を話す。
そこで福建語を話す年寄りの為に字幕が出る。

これを読むと、かなり内容が分ったような気になる。
漢字が共通語になり、お互いに少しは理解し合えるのは都合が良い。
韓国やベトナムは漢字を止めてしまったので、文字では全く理解し合えない。
テレビを見ていて分ったことがある。
北京語というのは、実にうるさい言葉なのである。
日本に来る中国人観光客がうるさいのではなく、北京語がうるさいのであった。


 2月の山中湖
2月の山中湖  丸ビル方面の夜景
丸ビル方面の夜景  ラーちゃん
ラーちゃん
 隅田川
隅田川  東京スカイツリー
東京スカイツリー