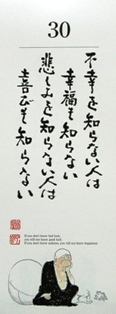■コーヒー談話
(2014年11月14日) 私が社会人になった頃はまだ日本は豊かではなかった。
その一方で先に豊かになった人達はその証のようにヨーロッパのブランド品を持ち、偉そうに自慢したり、その講釈を語るようになった。

私はそんな人達を苛立ってバカにして見ていた。
「自分では高くて買えない」というヒガミもあったのかもしれない。
「時計はオメガ」、「ライターはカルチェ」、「万年筆はモンブラン」などである。

それがしばらく経つと、時計はデジタルとなり1000円になった。
ライターは100円ライターとなった。万年筆は3本100円のボールペンになった。
そして、ブランドに拘っているのが恥ずかしい時代になってしまった。

それが現在では、「ライターは禁煙で不要」、「時計と万年筆はPCやスマホに付いている」ということで、ブランドの3種の神器は消えてしまった。
ところがそんな中でコーヒーは工業製品ではないので、講釈師も存在することが出来た。

昔はコーヒーの銘柄に始まり、産地、焙煎、挽き方、淹れ方、飲み方まで偉そうに講釈を垂れる人がいて迷惑だった。あの時代には、それが文化人の証でもあったのである。
しかしドトールを初めとする庶民的なコーヒーチェーンが出来て来て、コーヒーもまた講釈師の出番が少なくなってしまった。

今やコーヒーは文化人を気取る人の飲み物ではなく、気楽に飲めるものとなり、数え切れないほどのチェーン店や個人のカフェが出来た。
しかも多くの店ではコーヒー1杯が、200円~280円というところに収まっている。

40年前にはコーヒー1杯の値段は80円~90円だったから、今がいかに安いか分る。そこでウォーキングを兼ねてコーヒー店巡りをして、コーヒーの値段を調べてみた。
それぞれの店にそれぞれの特徴があるが、みんな努力をしているのが分った。そんな中でカフェとは違い座ることは出来ないが、バカに出来ないのがセブンイレブンの100円コーヒーだった。

昔ながらの喫茶店である日本資本のルノアールも、値段は高いが頑張っている。
(おまけの話)
私が初めて家でレギューラー・コーヒーを飲んだのは、かなり奥手で35歳の頃だったと思う。
女房が料理教室の生徒から、お歳暮でコーヒー豆をもらった。
我が家はそれまではインスタント・コーヒーばかりで、家でレギュラーコーヒーを飲む習慣が無かったので、豆の処理に困り近くのコーヒー豆専門店に行ってコーヒー豆を挽いてもらった。

しかしプレゼントしてくれた人に私は、「私の家ではいつも自分で豆を挽き、ドリップ式でコーヒーを飲んでいる」というような嘘を言った。
そしたら、またしばらくして、その人からコーヒー豆をもらった。
そうなるともうもらった豆だけを店で挽いてもらうのが恥ずかしくなり、その店でコーヒーミルを買った。
恥ずかしながら、それが私が我が家でコーヒーを飲むようになったキッカケなのである。

ジョン・レノンが愛した喫茶店。(歌舞伎座の裏)
その店のオヤジがコーヒーに詳しく、世界中のコーヒーの産地に行ったことがあると聞いた。オヤジのお勧めで「トラジャ」というインドネシア産のコーヒーを飲むようになり、今に至る。
先日のテレビ番組で見て初めて知ったが、「トラジャ」というのはインドネシアのトラジャ族という少数民族の名前であった。


 2月の山中湖
2月の山中湖  丸ビル方面の夜景
丸ビル方面の夜景  ラーちゃん
ラーちゃん
 隅田川
隅田川  東京スカイツリー
東京スカイツリー