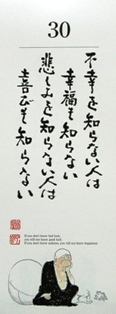■私も昔は小学生だった
なぜか最近は昔のことが思い出される。
「年をとった!」ということかな?
私は当時の小金井町立第2小学校に通っていた。その時の話である。
その頃は学校の周りは畑ばかりで、生徒数も少なくクラスは3つだった。

その他に「特殊学級」というクラスがあった。
特殊学級というのは、教育上、特別な支援が必要な生徒達を集めたクラスで、知的障害児童が属していたように思う。

さて学校の周りを取り巻く畑の話に戻るが、冬になるとその畑には霜柱が立った。
すると先生の命令で、生徒達は畑に行って「麦踏み」をさせられた。
その時は「なぜ麦踏みをするの?」と、良く分らなかったが面白かった。

でもいま考えると「秋に植えた麦が霜柱で根が浮いてしまうので、それを生徒達が横一列に並んで踏みつけて根付きを良くしようとした」のだろう。
その頃は戦後間もなくで食料不足の時代だったし、農家も人手不足で農家が小学校にお願いしたのかもしれない。今でいうところのボランティアだった。

小学校では豚と鶏を飼っていたが、なぜだか分からない。
教育の為だったのだろうか?
その豚の面倒を見るのは生徒達の仕事で、当番制になっていた。
学校のある日は、宿直のオジサンが餌を用意してくれた。

夏休みになると当番になった生徒は、家から豚の餌になりそうな余り物を持って学校に行った。
その時に先生に言われたことを覚えている。
「豚は辛い物を与えると死んでしまうので、カレーなどは駄目です」。
そういえば、少し前に豚が死んだことがあったが、それだったのかも?

私は当番の日に、家から余り物を運んで豚に食べさせた。
何を持って行ったかは覚えていない。
でもその後、いつの間にかその豚はいなくなったが、どうなったのだろう?

(おまけの話)
1年生から6年生までの間、私の担任になった先生は女の先生だった。
私の母親と同じような年齢だったが、とても気が強く怖かった。
生徒が悪さをすると、教壇からチョークを投げ付けた。

それでも悪さを止めないと、前に引っ張り出して頭を掴み黒板に吊り下げた大型算盤に生徒の頭を打ち付けた。算盤玉は円錐形なので、角が尖っているのでとても痛い。
そこに頭をぶつける先生は、今なら親から訴えられる。
その先生も55歳で定年となり、私が結婚する時には披露宴にも来てもらった。

その後、しばらくぶりに家の近くで出会ったら驚いた。
着物をはだけて朦朧として歩いていた。きっとボケて徘徊していたのだろう。
私の担任の時は気が強く、キリっとしていた先生だったのに。
その姿を見て、私はとても悲しかった。
「先生はボケやすい」と言われているが、まさにそうなってしまった。


 2月の山中湖
2月の山中湖  丸ビル方面の夜景
丸ビル方面の夜景  ラーちゃん
ラーちゃん
 隅田川
隅田川  東京スカイツリー
東京スカイツリー