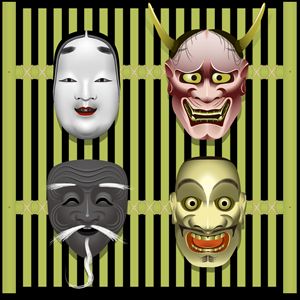■八郎潟
秋田県鹿角草木の村に、昔八郎太郎という名前のマタギがいた。若いが優秀な男であったという…。ある日の事、仲間のマタギと連れ立って十和田の山に猟に出かけた。その日、晩飯の準備は八郎太郎が当番となり、岩魚を焼いて仲間の帰りを待っていた…。
しかし、あまりに岩魚の匂いがおいしそうなもので、ついつい食べてしまった。すると激しく喉が渇き、焼けるような感覚に悶絶した。夢中になって水を飲み続けていると、八郎太郎の身体は次第に蛇身となっていき、最後には大蛇と変わり果ててしまったという…。仕方なく八郎太郎はそこに大きな湖を作って住みついた。これが現在の十和田湖だと伝えられている。
 それから長い年月が流れた。十和田湖に南祖坊という修験者が熊野権現のお告げと称し住みつく事になった。それをよしとしない十和田湖の主である八郎太郎と、南祖坊との法力合戦が始まった。八郎太郎は敗れ、十和田湖を出て天瀬川に逃れる…。そこで、八郎太郎は老翁と老姥に助けられた。お礼に八郎太郎はここに大きな湖を作るから鶏の鳴く前に逃げるように2人に忠告した。しかし、忘れ物を取りに行った老姥は大洪水に巻き込まれそうになってしまう…。八郎太郎は老姥を助けるために尾を使い岸辺に投げ飛ばしたが、老姥と老翁は対岸に離ればなれなってしまった…。
それから長い年月が流れた。十和田湖に南祖坊という修験者が熊野権現のお告げと称し住みつく事になった。それをよしとしない十和田湖の主である八郎太郎と、南祖坊との法力合戦が始まった。八郎太郎は敗れ、十和田湖を出て天瀬川に逃れる…。そこで、八郎太郎は老翁と老姥に助けられた。お礼に八郎太郎はここに大きな湖を作るから鶏の鳴く前に逃げるように2人に忠告した。しかし、忘れ物を取りに行った老姥は大洪水に巻き込まれそうになってしまう…。八郎太郎は老姥を助けるために尾を使い岸辺に投げ飛ばしたが、老姥と老翁は対岸に離ればなれなってしまった…。  その後、老姥は姥御前として芦崎に祀られ、一方老翁は三倉鼻にて夫殿権現として祀られたという…。鶏の鳴く合図で老夫婦が別れ別れになってしまった事から、同地では鶏の卵を食べる事を禁ずる習慣さえ生まれたという…。この時、八郎太郎が作った湖が後の「八郎潟」ですね…。
その後、老姥は姥御前として芦崎に祀られ、一方老翁は三倉鼻にて夫殿権現として祀られたという…。鶏の鳴く合図で老夫婦が別れ別れになってしまった事から、同地では鶏の卵を食べる事を禁ずる習慣さえ生まれたという…。この時、八郎太郎が作った湖が後の「八郎潟」ですね…。 八郎潟が干拓された今、八郎太郎の心中穏やかではないと思いますけど、河川の脅威は蛇体で表現されるケースが多いのも事実。ある種の土木技術集団の象徴であるのか、あるいは単に蒸発と降雨で回転する水の流転を蛇体にあてはめたのでしょうかね…?