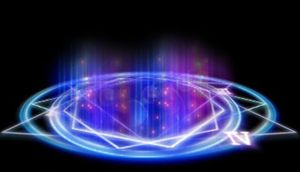■禁足地
何等かの事情で、人の立ち入りを禁じている場所が、日本各地にありますよね?その多くは神社や寺院にある神域や聖域で、名ばかりのところもあれば、関係者や地域住民が古くから守られてきた決まりを重んじて大切に崇めているところも多いですよね?いわゆる”禁足地”と呼ばれる場所でして…。
実は、都心からわずか30分の場所にも伝説的な禁足地がある事知ってますかね?
千葉県市川市、JR総武線本八幡駅から国道沿いを進むと、ほどなくして小さな森に出くわす。四方は石塀に囲まれていて、面積は20平方メートル程度だから、さほど大きくはないのだけど、正面には「不知森神社」と書かれた古びた鳥居と小さな祠がある。森といっても大半が竹なんで、竹藪ですわ…。
 ここは「不知八幡森」もしくは「八幡の藪知らず」と呼ばれる場所で、地域では足を踏み入れてはいけない領域として古くから畏れられて来た…。というのも、古くからこの森には数々の不気味な伝承が存在したためでして…。
ここは「不知八幡森」もしくは「八幡の藪知らず」と呼ばれる場所で、地域では足を踏み入れてはいけない領域として古くから畏れられて来た…。というのも、古くからこの森には数々の不気味な伝承が存在したためでして…。 不知八幡森は、少なくとも江戸時代には立ち入ってはならない場所として知られていた。その理由に定説はなく、葛飾八幡宮を最初に勧請した聖地であるとか、大和武尊の陣所、あるいは貴人の古墳の跡だといった聖域説と、平将門を討った平貞盛がここで八門遁甲の陣を敷き、死門(あの世への入り口)の一角を残した、また平将門の首を追い求めた家臣6人が入り込み、怨念を抱いたまま泥人形になったという逸話がある等、実にさまざまで…。
実は、昔この禁足を破った人物がおりまして…水戸光圀公。水戸黄門ですわ!この近くを通りかかった水戸光圀公が、藪の噂を聞きつけ周囲の制止を振り切って足を踏み入れた!昼間にもかかわらず道に迷った光圀公は藪の中で神の怒りに触れ、命からがら脱失した後に、住民に「ここには絶対に立ち入らないように!」と言い渡したという。このエピソードは後に錦絵にも描かれていますわ。この話に尾ひれがついて、不知八幡森は入ったら二度と出られない、神隠しの森として全国的に知れ渡るようになった…。そして、いつしか「八幡の藪知らず」という言葉は、迷い込んで出口が見つからないことを表す喩えとして用いられるようになり、今では広辞苑にも記載されている…。
 ちなみに現在、もっとも有力な説は次のとおりで、葛飾八幡宮では、その昔「放生会」という神事を執り行っていた。これは魚や鳥獣を野に放して殺生を戒める供養の儀式であって、この藪にはそのための魚等を生かしておく放生池があった。いつしか儀式の風習は途絶えたが、藪には禁足というタブーだけが残ったのではないかというものであって…。
ちなみに現在、もっとも有力な説は次のとおりで、葛飾八幡宮では、その昔「放生会」という神事を執り行っていた。これは魚や鳥獣を野に放して殺生を戒める供養の儀式であって、この藪にはそのための魚等を生かしておく放生池があった。いつしか儀式の風習は途絶えたが、藪には禁足というタブーだけが残ったのではないかというものであって…。 地形的にもこの敷地の中央は不自然に窪んでいるため、それが池だったとする説には説得力ありますよね?ただ、それが転じてか、落ちれば二度と助からない底なし沼があるという怪談まがいの言い伝えも同時に存在した事から、いずれにせよ、ここが昔から、あの世とこの世の境のような雰囲気をかもし出していたのでしょうね…。実際に訪れてみれば分かるんですが、森は子供一人でも迷いようがない程度の小さな森で、向かいには市役所が建ち、人通りも多い。