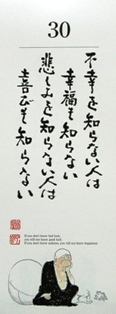■本場アメリカのハロウィーン
女房の従弟からメールで、本場アメリカのハロウィーンの写真が送られて来た。そこには次のようなことが書かれていた。 「Halloween が近付いて来ると、その飾り付けがアチコチで見られるようになる。骸骨や死人や墓地や悪魔や怪人、コウモリ、蜘蛛の巣、そしてパンプキン。どれも”ばっかみたい”だけど、またそういう行事やパーティに誘われる」

(ブログ掲載は許可済)
「今回は絵描き仲間の友達がその家と庭を開放してくれて、我々はそこで絵描きをする行事に招待された。家から15マイルの静かな郊外の住宅地に小農場付の家があり、そこには馬、ポニー、鶏、ガチョウが、そして室内には猫が6匹いる。全くのカントリースタイル。家のキッチンもアメリカン調で、いたるところにハロウィーンの装飾がしてある。」

「シャンデリアも10個ほどの骸骨で出来ていた。庭にはパンプキンがさりげない転がっているふうにしてあるが、その配置は熟慮の末だと分かる。フレンドリーな黒馬、その馬と仲良しのガチョウ、庭のコーナーのトウモロコシ畑、アメリカの田舎らしさをノスタルジックに表現している。
季節感の殆ど無い、したがって俳句の季語のごく稀なこの南カリフォルニアの地にあっては、ハロウィーンは数少ない季節感をもたらす時である」。

東京でも毎年、ハロウィーンの時期になると、渋谷あたりに若者が集まってバカ騒ぎをする。ところで彼女、彼らは「ハロウィーンってなに?」を知っているのかなー?
仏教徒の私はキリスト教の行事を知らないので、調べてみた。
「アメリカではれっきとした伝統行事。ハロウィンとはそもそも、カトリックの万聖節(AllSaint’s Day)の前夜祭のこと。ちなみに万聖節とは、聖人たちを讃えるためのお祭りで、ハロウィンの語源も、「神聖な(Hallow)」と「夜(Evening=een)」から来ている。

「Trick or Treat」の意味は直訳すると「トリック(魔法)をかけられたくなかったら、トリート(お菓子)をよこせ」ということ。これは19世紀のヨーロッパが発祥地という説が濃厚。万聖節の翌日である11月2日は死者の日。
「オール・ソウルズ・デー(All Sauls’ Day)」と呼ばれ、その昔、キリスト教徒らは死者の霊魂を天国へ導くお祈りをする代償として、「魂のケーキ(Soul Cake)」を乞いながら村中を練り歩いたというのが起源。

ハロウィンの象徴ともなっている「カボチャのランタン」は英語では「Jack-o’-Lantern(ジャック・オー・ランタン)」といい、アイルランド移民がアメリカに伝えたと言われている。昔、ケチで嘘つき、おまけに大酒飲みのジャックという、とんでもない男がいた。
ある日、酒を買うお金が底を尽きたジャックは、思案した挙句、こともあろうに悪魔をだまして銀貨を手に入れた。

年月が流れ、ジャックの寿命も終わってしまったが、生前の悪行の行き過ぎで、ジャックは天国はもちろん、地獄からも門前払いを受ける。
行き場を失ったジャックは、悪魔から石炭に火をつけたカブのランタンをもらい、それを灯しながら永遠に冥界をさまよい続けた。
民話にもあるように、オリジナルはカボチャではなく、カブ。
だからケルト人の末裔でもあるアイルランド人は、カブでランタンを作っていた。しかしアメリカに渡って来たアイルランド系移民たちは、カラフルで可愛いカボチャでランタンを作り始め、今のスタイルが定着した。

(おまけの話)
昨年のハロウィーンの時は、わざわざ渋谷に行って若者の仮装の写真を撮った。この年になると、一緒にハロウィーンを楽しむなんて気にはならなかった。
「日本人がなにをやってんだか!」と冷めた目でファインダーを覗いていた。遅い時間になると過激な仮装をした若者が溢れるようだが、私は午後8時には引き上げた。

もう昨年の取材で呆れてしまった私は、今年はハロウィーンなんて忘れていた。ところがアメリカからの写真で、また目が覚めてしまった。
そこで今年は渋谷ではなく、手近な銀座の様子を見に行った。
ネットで4丁目角の三愛ドリームセンターにプロジェクション・マッピングでハロウィーンの映像が映し出されると知ったからだ。

夜8時少し過ぎに写真を撮りに行った。
銀座4丁目の角で、三愛ビルを狙う。しかしいつまで経っても映像が始まらない。三越の前にいたガードマンに聞いてみたが、「そんな映像を流しているのは、知りません」と言われた。
30分待ったが、始まらないので、家に帰る。
どうやら31日のハロウィーンの日だけのイベントのようだ。


 2月の山中湖
2月の山中湖  丸ビル方面の夜景
丸ビル方面の夜景  ラーちゃん
ラーちゃん
 隅田川
隅田川  東京スカイツリー
東京スカイツリー