小石川後楽園に花菖蒲を見に行ったが、その時に「せっかくだから、小石川後楽園の様子も知らせた方が良いのでは?」と思った。我が家から小石川後楽園に行くには、大江戸線で「飯田橋駅」の最後部で降りて徒歩5分である。
入口で入園料を支払う。同じ東京都の庭園なのに、清澄庭園は70円、小石川後楽園はは150円だった。入園料の差は、庭園の広さで決めているのかもしれない。
騒々しい飯田橋・神楽坂から、静寂の小石川後楽園にやって来た。庭園内に入ると、「いいなー」と感じる。

園内に入ると目の前に大泉水が広がる。
まずは小石川後楽園の説明から入る。
『小石川後楽園は、江戸時代初期の寛永6年(1629年)に水戸徳川家初代藩主・徳川頼房(よりふさ)が江戸の中屋敷(明暦の大火後に上屋敷となる)に築造し、2代藩主・光圀の修治により完成した江戸の大名庭園として現存する最古の庭園です・・・』
『 園内は、「大泉水」の「海」の「景」を中心に、これをめぐる周囲に「山」「川」「田園(村里)」などの「景」が連環して配置されており、変化に富んだ風景が展開する「回遊式築山泉水庭園」です。・・・』。

飛び石で小川を渡る。
『池を中心にした回遊式庭園としての庭園形式は、江戸の大名庭園の先駆けとして後に造られる大名庭園にも大きな影響を与えました。中央に位置する「大泉水」をはじめ園内の多くの泉水は、江戸時代には、神田上水によってまかなわれていました。武家屋敷の邸内を上水が流れる例はまれで、現在は「神田上水跡」にその痕跡を見ることができます』。

「白糸の滝」
『後楽園の名は中国の「岳陽楼紀」の「天下の憂いに先だって憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ」から付けられた』そうだ。
日本は中国の古典から受けた影響が大きいが、今になって私はそれを感じる。
「現在の中国は偉大な昔の古典や偉人の言葉を、全く無視しているのでは?」・・・と。或いは過去は全く勉強していないのかもしれないなー。

「菖蒲田」
庭園に入り紅葉に時期には行く左の方の山は、今回はパスした。
大泉水を左に廻って歩いて行く。
「白糸の滝」から流れ出る小川を、飛び石伝いに渡って行く。
以前ならなんとも思わなかったのに、今回は足元に気を付けるように歩く。
少し先の左手が開けている。先の方に菖蒲田が見える。その前には小さな稲田もある。
米不足の今だから、稲田が気になり覗いてみた。

日陰の小道を進む
「菖蒲田」には大勢の観光客が来ていた。
見学用の木道は一方通行になっているが、立ち止まって写真を撮る人ばかりでなかなか先に進めない。菖蒲田を見てから更に奥に行った。
ここは彼岸花が綺麗に咲く場所で、今までに何度も来ている。
小石川後楽園はオールシーズンで楽しめるので、高齢者に人気があるのだろう。
大泉水に戻って、池の周りを歩いて先に行く。
この公園は割合に日影があるので、暑い日にはとても助かる。

庭園の反対側から見た大泉水
大泉水の反対側に来た。
ここにも「蓬莱島」という名の中の島があるが、橋も無く渡れない。
更に進み「睡蓮の池」を見た後に、林の中を通って出口に向かう。
林を抜けたところに休憩場所があり、いくつかのベンチが置いてある。
みんなも暑くて参っているのか、ベンチに空きは無かった。
ベンチに座り風に吹かれて大泉水を見ながら、冷たいものでも飲みたかったなー。

出口に近い休憩場所
(おまけの話)
小石川後楽園には2つの入口がある。
地下鉄やJRで飯田橋駅から行く時は西門から入るが、こちらが正門である。
庭園の一番奥にある入口は「東門」で、JR水道橋駅から来る時に使う。
東門を入ると、目の前に「水蓮の池」が広がる。ここは「内庭」と呼ばれている。
6月は睡蓮の季節で、たくさんの小さな白い花が咲いている。

内庭の「蓮の池」
池は左右に分かれていて趣のある橋が架かっているが、渡ることは禁止である。
今年の睡蓮は例年とは少し違うようだ。
睡蓮が東門の方に偏っていて、私が行く西門方向にはあまり浮いていない。
だから花も反対側に行かないと、多くは見られない。どういう理由かは分からない。
東京都の大名庭園には、昔の実業家から寄贈を受けたものが多い。
なぜそんなに高額な庭園の寄贈が多いのかが、凡人の私には疑問だった。
これをネットで調べてみたら、色々と面白いことが分かった。
その理由は「社会の文化財を私有する心の重さ」、「所有と維持の莫大な負担」、「名前を残したい」などがあるようだ。
ここでは書き切れないので、暇な時に調べて読んでみて欲しい。
論文のタイトルは「東京都の寄贈公園と岩崎久弥翁」に詳しい。

睡蓮の花が咲いていた
\ この記事をシェアする /







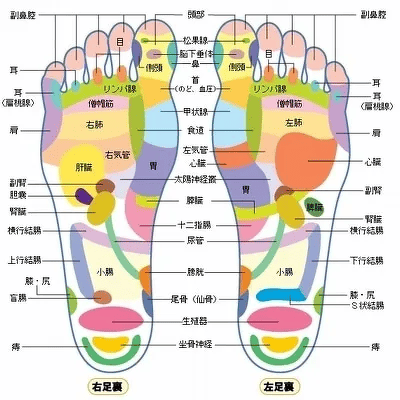











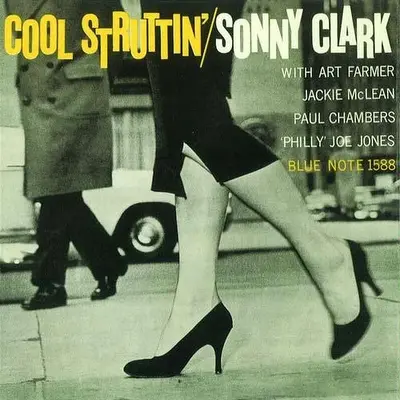
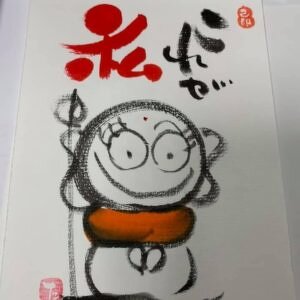



コメントはまだありません。
コメントを書く