日比谷公園のHPを見たら、「竜舌蘭が咲いた」と出ていた。
私は竜舌蘭の咲いたのを見るのは、これで2回目だった。
2022年3月に築地川公園で、一度に3本の竜舌蘭が咲いて、それをブログに載せた。
『雪の中で竜舌蘭を見る』・・・・https://mushanavi.com/author/jiyujin/blog2/entry-7079.html
だから私にとっては珍しくもないのだが、「70年に一度咲く」という花なので、せっかくだから見に行った。昼頃に現地に行ったら、15人くらいの人達が来ていて、熱心に写真を撮っていた。ここの竜舌蘭は7メートルくらいの高さがあるので、花の様子はよく見えなかった。私には「冥途の土産」にはならなかった。
この日は天気予報では「雨」だった。日本各地で大雨による被害も発生していた。
千代田区の正午の気温24.5度、湿度51%で、割合に過ごしやすい天気だった。
雨も降らず、公園を散歩する人、ベンチで語るカップル、私のようにブラブラしている人達がいた。
有楽門から入って竜舌蘭の植えてある「第一花壇」の奥には、ノウゼンカズラのオレンジ色の花が咲いていた。いまが見頃のようだ。
バラも植えてあるが、そろそろ終りの時期を迎えている。
枯れかかったバラが多い中で、ピンク色のバラだけが元気だった。
後ろに見える裸婦像は、タイトルが「自由」だった。
第一花壇を抜けて、銀杏並木に出る。
青いギンナンでもないかと上を見上げたが、見付けられなかった。
テニスコートの横の細い道を、外国人の家族が入って行った。
ここの右側は、春は彼岸花が咲く。
右側にはヒマワリが植えられているが、まだ少し早いようで、小さな花が2輪しか咲いていなかった。
銀杏並木に戻り、先に進む。
左手に100円カレーで有名な「松本楼」を見ながら進む。
その先の小道を左に入れば、「鶴の噴水」がある。
この近くに盛大に咲いていた「ユリ園」があり、少し前に写真を撮りに来た。
しかし「少し前」と思っていたが、それは手帳を見たら「6月22日」だった。
残念ながら、もうユリの花は終り、「カサブランカ」だけが少し咲いていた。
仕方ないので「鶴の噴水」を見に行こうと歩いていたら、ユリの葉の裏側にセミの抜け殻が付いているのを見付けた。
忙しかった現役の時と違い、引退すると色々なものが目に入って来る。
いつもブログネタを探しているからかもしれない。
都心で「セミの抜け殻」を見たのは、初めてだと思う。
この時期になると、鶴の噴水の池は緑に覆われる。
葉が茂り、池の中だけポッカリと空間が出来る。
藤棚のある場所では、みんなベンチに座り池を眺めたり、本を読んだりしている。
「平和だなー」と感じる時間である。
近年はあまり寒くならないので、鶴の噴水は凍らず、鶴の羽から下がるツララも見ることが減った。それがとても残念である。
(おまけの話)
今まで気が付かなかったが、藤棚の横の水の中に「ガマの穂」が生えていた。
この時期に来ないので、知らなかっただけである。
いつものようにネットで「ガマの穂」を調べたら、面白いことが書いてあった。
『ガマの穂は爆発します』と、書いてあったので驚いた。
『火を放って大きな音が出るのではなく、膨らんだガマの穂を手で潰すと勢いよく破れる。そして種を飛ばして繁殖する』とあった。
なんでも興味を持って調べると、思い掛けない情報もあるものだ。
鶴の噴水を離れて、日比谷公会堂方面に向かう。
日比谷公園大音楽堂(野音)の前に、若者が長い行列を作っていた。
「なんだろう?」と思い覗いてみたら、「楠木ともり」という女性のコンサートの開場待ちと、グッズ販売の順番待ちだった。
私は彼等より、会場前の大きな「松ぼっくり」に目が行った。なにしろ大きい。普通の「松ぼっくり」の3倍はある大きさだ。
これはヒマラヤ杉の「松ぼっくり」だが、杉でも「松」ぼっくりでいいのだろうか?
ヒマラヤ杉は「マツ科」なので、「松ぼっくり」でいいのかもしれない。
「野音」を通り過ぎて出口に向かうと、右手に「日比谷公会堂」が見えて来る。
この建物は1929年に開館したが、最近は老朽化が進み2016年から休館となっている。
東京都は建て替えと運営を民間業者に発注のために、公募を行ったが応募が無かったという「いわくつき」の建物である。
建物前には巨木が何本かあり、そこには丸い実がたくさん下がっている。
この木は「スズカケ」の木で、「鈴を吊り下げたように見える」ことから、「スズカケ」となったのだそうだ。
\ この記事をシェアする /







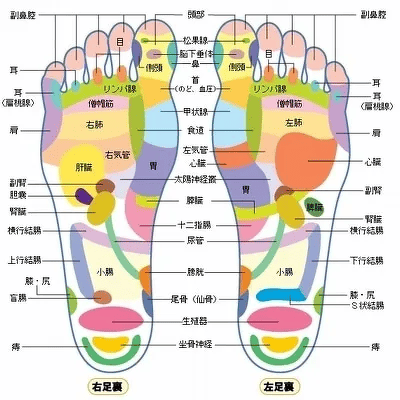











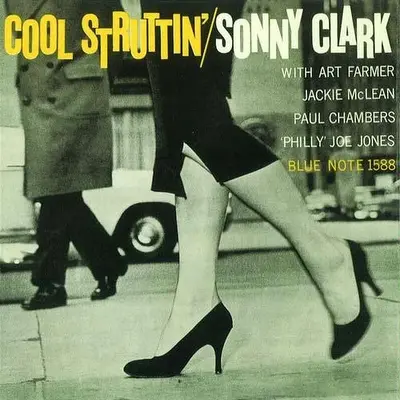
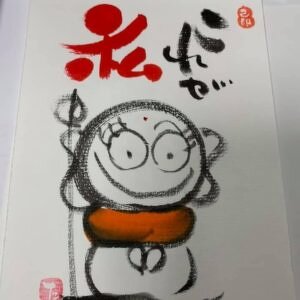












コメントはまだありません。
コメントを書く