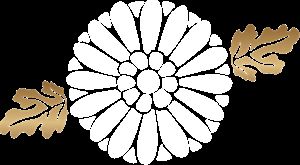■神宮
「××神宮」という名称の神社って、どこか別格で荘厳なイメージないですかね…?何せ「神の宮」ですからね…。神社ってよく見ると色々な肩書のようなものがついている。神宮以外だと「大社」「明神」「権現」「稲荷」等々…。では、神宮はそれらとどこが違うのか?というと…。元々神宮は、どの神社でも自由につけられるものではなかった!
何しろ「神宮」はかつて伊勢神宮しかなかった!だから伊勢神宮の正式な名称は”神宮”であって、他にないのですからこれで十分だったのさ…。「日本書紀」を見ても、伊勢神宮と石上神宮の2社しかなく、平安時代に成立した「延喜式神名帳」を見ると、石上神宮に代わって鹿島神宮と香取神宮が「神宮」と記載されている。以降、江戸時代まで日本には「神宮」とつけられた神社は、伊勢、鹿島、香取の3社しか存在していなかった!

確かに、伊勢神宮は皇祖神アマテラスを祀る神社であり、鹿島神宮のタケミカヅチと香取神宮のフツヌシはオオクニヌシに国譲りを認めさせた功労神で…。「明治政府…」と書いたのは、「神宮」を名乗るには勅許が必要だったからで、勝手に名乗る訳にはいかなかったというのはそういう理由からで…。
実際のところは、近世になるまでは「神社」や「大社」、あるいは「宮」といった社号に特別な基準等なかった。しかし、明治時代になると、国家神道の政策のもと、神社に対する管理が厳しくなっていく。何故なら明治から終戦までは、神社は国の施設のようなもので、全ての国民がどこかの神社の氏子になる事が定められていた。そのため、神社として認められるためには厳しい基準があったのさ…。

それでも「神宮」というのは敷居が高いのか、新興宗教系教団や伊勢神宮の分霊を除けば、戦後「神宮」に改称したのは、北海道神宮(旧札幌神社・北海道)、伊弉諾神宮(兵庫県)、英彦山神宮(福岡県)と、神社本庁から独立して改称した新日吉神宮(京都府)等、わずかしかない…。