■端午の節句
5月5日は「こどもの日」ですよね…。端午の節句とも呼ばれていて、男の子の成長を祝う日として知られていますが、古来この行事は女の子のためのものであった事知ってますかね?山神として古代人に崇められていた”サ神”サガミ様が宿る”座(クラ)”がサクラなんですけど、そろそろ田植えが始まろうか?という時期、サ神が里に降りて来るその月は、いつしか「サ月」=皐月、五月と呼ばれるようになった…。
選ばれた乙女たちは豊饒を願い、小屋や神社に篭って、サ神のために身を清めて穢れを祓う…。彼女たちは「サ乙女」=早乙女と言われたのさ…。
 「五月忌み」という名で知られるこの儀式を、端午の節句の起源とする説が根強い。原始的なアニミズムの風習がきっかけらしい…。
「五月忌み」という名で知られるこの儀式を、端午の節句の起源とする説が根強い。原始的なアニミズムの風習がきっかけらしい…。 「五月忌み」はまた、流行り病を表す言葉でもあって、旧暦の5月5日あたりは、今で言う梅雨の時期でもありますもんね…。
湿度も気温も上がり、衛生状態が悪くなって、食中毒や伝染病等が、現代よりも広範囲に深刻にはびこっていたに違いない。感染を避けるための厄除けの意味もあったのさ…。端午の節句に菖蒲湯に入るという今でも続いている風習も、神事として身を清めるだけでなく、薬草でもある菖蒲を使って病気を予防したり抵抗力をつける意味合いがあったようなの…。
 武家社会の時代になって、女児よりも男児に重きが置かれる世の中になって行く中で、端午の節句も男の子のお祭りへと変化して行く。菖蒲はその読み音から「勝負」「尚武」とも解釈され、特に武家の男子を盛大に祝う風潮が作られて行く…。
武家社会の時代になって、女児よりも男児に重きが置かれる世の中になって行く中で、端午の節句も男の子のお祭りへと変化して行く。菖蒲はその読み音から「勝負」「尚武」とも解釈され、特に武家の男子を盛大に祝う風潮が作られて行く…。 端午の節句と言えば鯉のぼりですが、荒々しい戦国の世にはためいていた軍旗が元になっていると言われている。それぞれの陣地を表す吹流しや、武者が背に刺した幟…。
端午の節句には家に鎧兜を飾る習慣も残っていますが、これもやはり武士の時代に由来する。「たくましい男の子に育ってほしい」という親心を映していると言われていますけど、その歴史は戦争の血生臭さを感じますよね…?
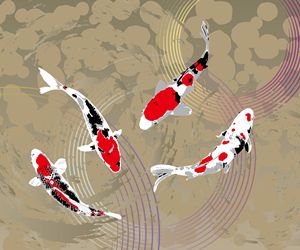
これに想を得た江戸時代の武士たちによって、鯉のぼりが考案されていった…。鯉のぼりは立身出世の象徴ですからね…。
