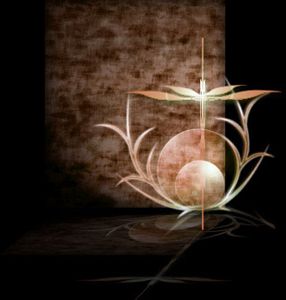■入れ墨
最近、意外とタトゥー入れてる方を結構見る…。あえて入れ墨と言わせてもらいますけど、世界中のあらゆる場所で、古代人類は入れ墨の文化を持っていた。北極圏から南極圏まで、様々な地域で、入れ墨は世界共通、同時発生的に生まれたとされている…。
サルから人類に進化する過程で失われていったのが体毛とされていますが、顔や全身を覆う毛は、敵と味方を識別したり、模様によって異性にアプローチする等、社会的な役割があった。その代替えが入れ墨だと言われている。古代の日本では誰しもが入れ墨をしていたと、「魏志倭人伝」にもある。この時代の埴輪にも入れ墨が施されていたりもしますしね…。
また体毛は、体温調整、クッション等、身を守るものでもあったので、人類はその代わりに入れ墨を施し、護身の願いを込めたんですよ。やがて呪術的な意味合いを持ち、特定の文様の入れ墨が、魔除けの効力があるとされた。死後、あの世に渡るために必要な「印」だという地域もあったようで…。関節痛や神経痛の治療として施される事もあり、沖縄や北海道の他、熊本県でも近年まで残っていた。現代の鍼治療に相当し、やはり古代から続いていた。