■蝦夷三官寺
寛政11年(1799)、幕府は太平洋沿岸地域である東蝦夷地を直轄領とした。北方警備の強化と、内地化政策を展開し、蝦夷地に派遣される幕府役人や勤番所の諸藩兵、出稼ぎ人等が死亡した時の供養のため、寺院の設置が提案された。当時、「新寺建立の禁」があったが、外国との境にある蝦夷地の特殊性により認められ、供養とキリシタン禁教、国家鎮護の役割を担い、官立の寺院として文化元年(1804)に三寺院の建立が許可された…。
和人地に近いウス(現伊達市有珠)には、古くから民間信仰の霊場があり、これを素地として浄土宗善光寺が設置され、山越内から白老までを管轄した。
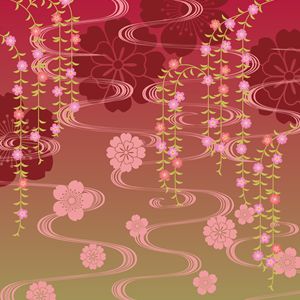
シャマニ(現様似郡様似町)に設置された天台宗等澍院は、勇払から襟裳までを管轄した。この地は東蝦夷地の中央に位置し、道路開削によって陸路の交通確保が図られた要地でもあった。
寺院の設置目的に、アイヌ民族への教化はないものの、寺院奉行からの掟には、「蝦夷をして本邦の姿に帰化せしむ事」とあり、布教活動があったとされている。
有珠善光寺では、念仏布教を説いた「念仏上人引歌」に、アイヌ語訳を仮名文字で表記した版木が作られていて、国泰寺にはアイヌ民族の死者への「供養」や「戒名」の記録が見られる。また、三官寺とも年中行事などにアイヌの人々を招いており、生活における交流の中で、布教が行われていたと思われますね…。

貴重な歴史的なお寺が、この伊達にもありますから、善光寺さんには、宝物殿等もあるので、是非ご参拝と見学に…。
