■三途の川
”冥途の旅”は冥途の法廷で計7回にわたって調べられ来世の行き先を決められるそうです。その裁判が、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日にあって、七七日の泰山王の法廷を過ぎると、死者は有名な川三途の川にさしかかるそうです。この川についてはインドの仏典には出て来ません。
また、日本でも浄土宗・浄土真宗の教えでは、南無阿弥陀仏で、真っ直ぐ阿弥陀如来の元へ行ける宗派だから、三途の川を渡る概念が本来ないため、死者に手甲・脚絆を付けない宗派もあるのですが…。
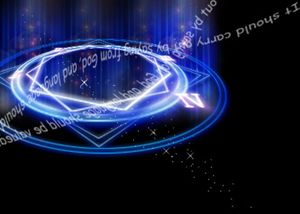
この川は冥界を横切ってとうとう流れる大河を誰でも渡らなくてはならないのは皆さんもよくご存じですよね…?
”三途の川”の由来は、向こう岸に渡るのに3通りの途があるというところから来ているそうです。つまり、死者の生前の行いの良し悪しによって渡り方が違って来るようなんですね…。一応、橋が架かっているのですが、この橋を渡れるのは罪の軽い人だけだそうで…。罪の重い者たちは川の中に入らなくてはならず、しかもそれにも軽重があります。比較的罪の軽い人は浅瀬、重罪の人は濁流を渡らなくてはならないようです。
そして、この”三途の川”の渡し賃が六文で、死者を納棺する時に入れる六文銭はこの時のためです。”三途の川”のほとりに立って辺りを見回すと、賽の河原が見えるようで、そこでは、大勢の子供たちが一生懸命に河原の小石を積んで塔をつくっている姿が見えるそうです。

そのために子供たちは、”三途の川”を渡してもらえず永遠に小石を積み続けているようです。
本来、死にたくて死ぬ子供いないと思うんですけど、不条理も感じますけどね…。
