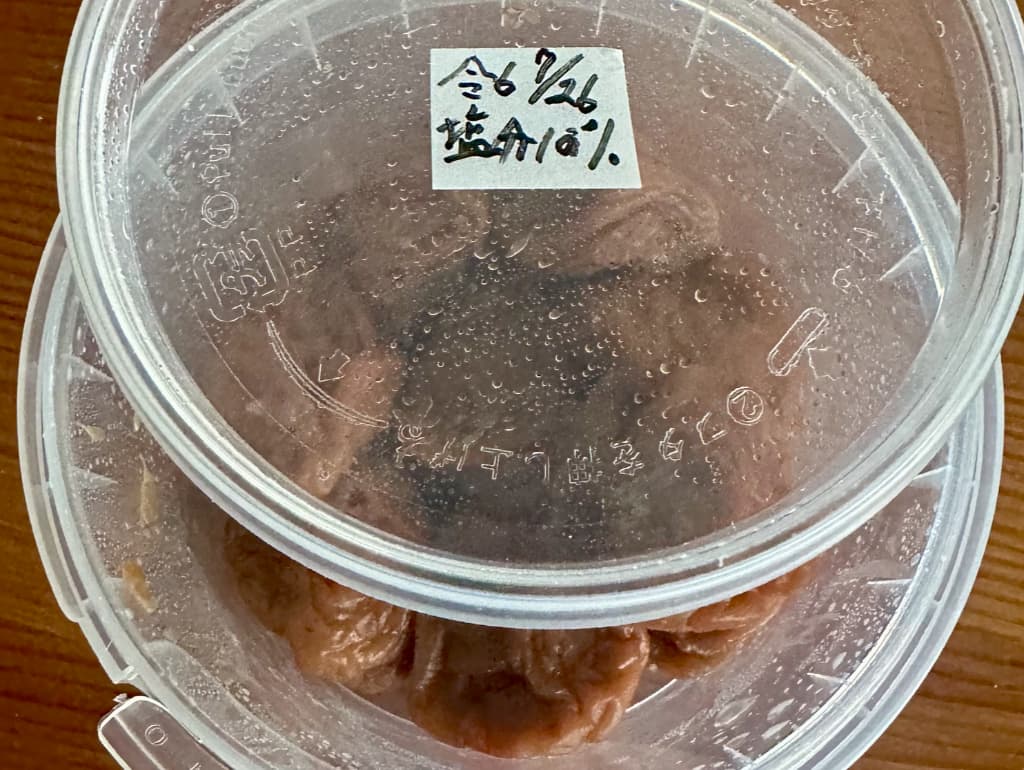
藤沢の91歳になる伯母が漬けた梅干しが、瓶の底にわずかばかり残るだけとなった。北海道まで届けられたこの梅は、二年ものから一年ものへと代わり、俺の手元で静かに消えようとしている。口に含むたび、塩気とともに蘇るのは、母の家族の物語だ。
その梅の木は今も、藤沢の地に根を張っている。かつて祖父母が営んでいた旅館の一角に立ち、白い花を咲かせ、青い実をつけてきた。祖母の手が、伯母の手が、何十年もの間大切にしてきた。旅館はもう取り壊され、跡地には伯母と従兄弟夫婦が住む。建物は消えて周りは住宅地となったが、あの梅の木だけは変わらずそこにある。
母方の家系は、徳川吉宗の時代から続く商家だった。代々の墓石が並ぶ墓地が、その歴史を静かに物語っている。祖父は商才に長け、不動産、金貸し、旅館と手を広げ、横浜界隈でハーレーのバイクに乗っていたというから商売はうまくいっていたのだと思う。だから三姉妹の生活も裕福だったはずだ。

だが、運命は容赦なかった。
三女の伯母は、幼い頃の日本脳炎による高熱で知的障害を負った。俺が「ピーちゃん」と呼び、旅館で無邪気に遊んだあの人。その笑顔の裏に、祖父母がどれほどの不安を抱えて生きてきたか、子どもの頃の俺には知る由もなかった。
本当に最近知ったことなのだが、祖母は戦う人生を過ごしたらしい。
当時、障がいを持つ子は隠され、人里離れた場所の隔離施設に入所させられた。だが祖母は違った。ピーちゃんを手元に置きながら通える施設を、自分の町に作ると決めたのだ。そこで同じ境遇の母親たちを集め、藤沢市に働きかけ、ついにそれを実現させた。その運動のせいで、母が学生だった頃、祖母はほとんど家にいなかったという。その情熱はすごかったのだと思う。
「この子がいる間は、私は死ねない」
幼少の頃からよく耳にしていた祖母が繰り返したその言葉が、今も耳に残っている。ピーちゃんを見つめる祖母の眼差しには、母としての覚悟が宿っていた。
やがて祖父が逝き、祖母もこの世を去った。最期の最期まで、ピーちゃんのことを案じながら。
その後を引き継いだのは、長女である伯母だった。早くに離婚した彼女はひとりでピーちゃんを支えてきた。その苦労は、言葉では測れない。
今、ピーちゃんは八十代となり、別の施設で元気に暮らしている。
そして、あの梅の木は、すべてを見ていた。三姉妹の青春を、祖母の決意を、正月恒例のピーちゃんと俺との羽つきの様子を、伯母の献身を、そして時代の移ろいを。今もその木は実をつけ、伯母の手で梅干しとなり、遠く北海道に移住した俺が食べている。瓶の底に残るわずかな梅干しを、俺は少しずつ、大切に味わう。塩辛さの奥に、母の家族の歴史が溶け込んでいる。梅の木が実をつける限り、この物語は続いていく。

\ この記事をシェアする /







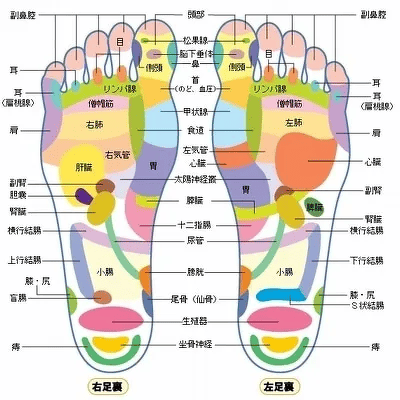
















kayakerさんのブログはいつも感動に満ちた物語です。
文章も上手だし、商社マンではなく小説家に向いていたのかもしれない。
ありがとうございます。いやいや、恥ずかしい限りです・・・・
いつか自分の末代が先祖の思いとかに触れる機会を夢見ながらその記録として書き残しているつもりです。どうしても昔の話が多くなるのは自分の中でも整理したいからなんでしょうね。これからもよろしくお願いします。