子供の頃から私たちが刷り込まれてきた価値観。それは「できるだけ無駄なく、効率的に人生を進める」ことだ。親や教師からそう教育され、世に溢れる自己啓発書もこれを基盤としている。家でダラダラ過ごすことは悪であり、目標やTo Doリストを持ち、時間を有効に使うことが「正しい生き方」とされてきた。その根拠は「人生は短い」「時間は有限だ」という至極真っ当な考え方にある。いつか死を迎える以上、それまでに多くのことを達成するために、時間を効率的に使うべきだという論理は一見、正しい。
だが、60歳を過ぎて現役を退く年齢を迎え、ふと立ち止まって考える。「果たして効率的に生きることは、本当に正解なのか?」
「人生の有限な時間を有効に使う」という考え方自体を否定するわけではない。しかし、「時間の観念」そのものが違えば、前提は全く変わり、そこから導かれる世界観もまた違ってくるのではないか。
先日、妻が91歳の父親の看病のため上京し、私はほぼ丸二日間、一人の時間ができた。普段、仕事場を自宅にしている私にとって、滅多にないこの一人の時間は、どうにもワクワクするものだ。
これまでは、この貴重な時間に何をしようか、と「やることリスト」を考えていた。しかし最近は、そのリストが具体的に頭に浮かばなくなった。そして、何をするか決めあぐねているうちに一日が終わってしまうというパターンが増えた。これはもしかしたら、二人でいる時でも既に自分のやりたいことが十分にできているからかもしれない。
いずれにせよ、そうしてダラダラと何も成し遂げずに一日を終えると、「もっと時間を有効に使うべく、事前に準備すべきだった」と、ある種の「後悔の念」が湧き上がってくる。

(つづく)
4
\ この記事をシェアする /







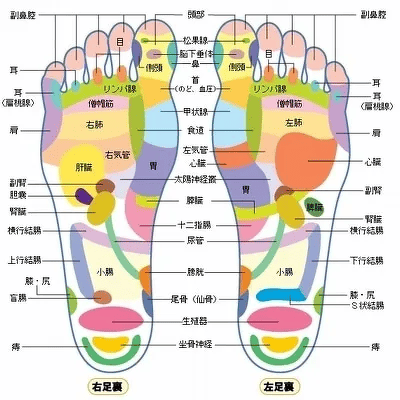











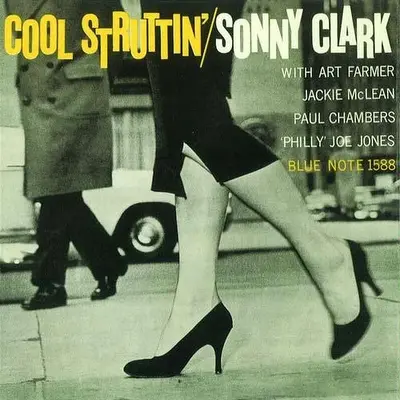
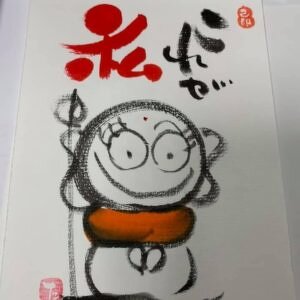



[…] (おまけの話)【終り方】「むしゃなび」のブロガーに「kayaker」がいるが、私は彼のファンで必ず読んでいる。10月20日のブログのタイトルで「無駄な1日を考える」があり、彼の記述が「その通りだった」と思って読んだ。「kayakerのブログ」・・・無駄な1日を考える(その1) | kayaker | むしゃなび blog『子供の頃から私達が刷り込まれてきた価値観、それは「できるだけ無駄なく、効率的に人生を進める」ことだ。その根拠は「人生は短い」、「時間は有限だ」という至極真っ当な考え方にある』。私もその考えで、真面目に人生を送って来た。そしていまは後期高齢者をとっくに過ぎ、日本人男性の平均寿命も越えてしまった。ここまで来ると考え方も変わる。「人生は短い」は間違いだ。「人生は長い」である。(写真の仏像は私が15年くらい前に、趣味で彫ったものです) […]