ブログ閉鎖中の話題(2015年9月28日)
7月に私が企画して同級生達と実行した「ステーキランチと銀座散策」が評判が良かったので、参加者の希望を入れて9月25日に今度は「築地徘徊ツアー」を企画した。
最近の私は年のせいか神通力が衰えてしまい、「晴れ男」の私には珍しく、その日は天候が急変して雨となってしまった。

今回の築地徘徊ツアーは、銀座4丁目交差点の三越デパート前から始まった。
同じ東京都に住んでいても、青梅や八王子の友人達は銀座は遠いと感じているようだ。
だから歌舞伎座が新築されてもう3年近く経つのに、みんな行ったことが無いと言う。
歌舞伎座の地下一階にある「木挽町広場」に行くと、歌舞伎関係のお土産が買える。

歌舞伎座の次は日本で最初にカツカレーを始めたレストランの「スイス」である。
本店は銀座3丁目にあるが、私の贔屓は10分ほど歩いた築地の路地裏にある。
銀座本店と違い気取りがなく、入り口の販売機で食券を買う。
ここのカツカレーは元巨人軍の千葉選手が「カレーにカツを乗せてくれ」と言ったのが始まりだそうだ。

カツカレーを食べた後は、次の築地本願寺へ向う。
ここは今年になって私が門徒になったお寺で、そのせいもありよく来るようになった。
午後12時20分から始まるパイプオルガンの無料コンサートを聴くのが目的で、お寺の本堂で聴くパイプオルガンの音色は素晴らしい。
【築地本願寺】・・・・・ http://tsukijihongwanji.jp/
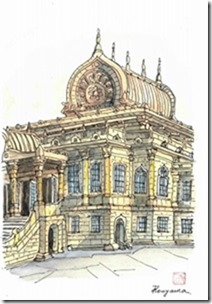
パイプオルガンのコンサートの後は築地市場である。相変わらずの観光客で場外市場は大混雑である。先ずはテリー伊藤の実家の「丸武」で串刺しの100円の卵焼きを買って食べる。これは結構美味しいので、私は太るのが分っていながらいつも買ってしまう。

次は波除神社で、場内市場に入る門のすぐ脇にある。
お歯黒の大きな獅子頭の前で記念撮影をする。
そこに来ていた白人の若い女性達にジジイの1人が声を掛けて、我々の写真に入るように言ったら、なんと1人が一緒に入ってくれた。話を聞いたらフランスから来たそうだ。

その次は場内市場を通り抜け、正門から外に出る。
目の前が憎き朝日新聞で、その隣が同級生のK君が総長を務めていた国立ガンセンターである。その並びに直木賞の審査が行われた料亭「新喜楽」がある。
雨が激しくなって来たので、今回の徘徊ツアーはここまでとする。

(おまけの話)
築地徘徊ツアーが終り、東劇前の松竹スクエア1階のカフェに入る。
ここは私のお気に入りの場所で、暇な時はここへ来てコーヒーを飲みながら本を読む。
1階の入り口から中に入ると広い空間が広がり、木製の階段状のスペースがある。
その一番上の3階相当の場所にカフェがある。

先に帰ったM君を除いた6人でお茶をしながら、今日の反省会をする。
最初の内は今日の旅の話をしているのだが、いつの間にかお墓の話になってしまった。
以前は病気の話が多かったが、遂にお墓の話になるような年齢となったのか・・・。
それも仕方ない。

左に座っている人達は「1幕観劇」のチケットを買うのを待っている。
観劇料は出し物により「1000~1800円」。チケットを買うのは外国人が多い。
実は今回の築地本願寺のコンサートの後に、みんなの希望を入れて私が今年になってから門徒になり、本堂真下にある納骨堂のロッカー式の買ったお墓を見せたからだ。
翌日の朝にPCを開いたら、昨日の私のツアーガイドのお礼のメールが来ていた。
その中にO君から「スイスのカツカレーも丸武の卵焼きも良かったですが、お気に入りは築地本願寺本堂下の納骨堂ですねー」とあった。 やはり墓が一番かー・・・。

\ この記事をシェアする /

北海道伊達市に2003年夏より毎年季節移住に来ていた東京出身のH氏。夏の間の3ヵ月間をトーヤレイクヒルG.C.のコテージに滞在していたが、ゴルフ場の閉鎖で滞在先を失う。それ以降は行く先が無く、都心で徘徊の毎日。
- アクセス総数
- 1,557,678回






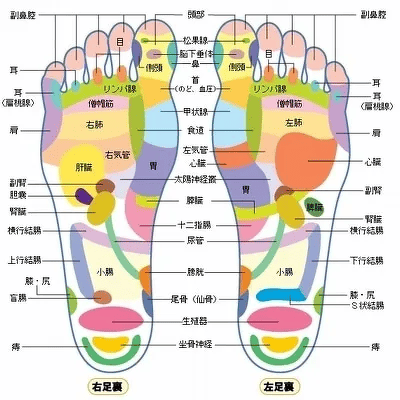











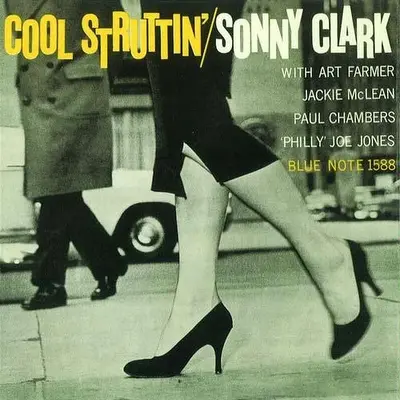
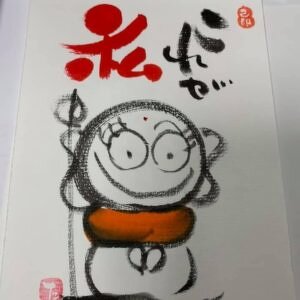



昔を懐かしむ歳になった。10年前には雨の中を元気に歩き回っていたのが、今ではよちよち歩きの徘徊である。それでも何とか食らいついて「都心を歩かない会」に参加している。
この根性の源は、同期生の仲間が《昔を知り、今を許し合える》ことに由来するのかもしれない。