ある雑誌で面白い対談を読んだ。鉛筆メーカーの社長と専務が、誰か忘れたが、著名人と話していた。社長が言った『鉛筆には他の筆記具にはない、2つの特長がある。1つ目は必ず書ける。2つ目は消すことが出来る』
当たり前と思っていたので、そうだったと気が付いた。
そこで私はこの会社をネットで調べてみた。会社の名前は北星鉛筆で、途中で関東大震災に遭い北海道に移転したりした後に、現在の四つ木に工場を構えたのだそうだ。ホームページには工場見学を行っていると書いてあったので、早速卯申し込んだ。
その日は台風10合が東京にも来そうな感じだったので、中止も覚悟していた。
ところが当日は朝から晴れていて、迷走台風は来ないようだった。
工場見学は午前10時から四つ木工場なので、余裕をみて9時前に家を出た。
京成押上線の四ツ木駅に降りるのは、私は初めてだった。
駅前は商店街もなく、道路も昔の畑道がそのまま現在まで残った感じで、とても分かりにくい。交番で聞いてやっと10時に間に合った。
事務所で社長の奥さんに参加費の400円を支払い、奥の部屋に入る。
そこへ社長が出てきて、今日の参加者が揃ったので始めますと言った。
私の他は小さな男の子を連れた母親で、全部で3人だった。
最初にNHKのテレビ番組で取材された、15分ほどの映像を見せられる。
それが終わると、社長の話になつた。
社長は鉛筆業界の最初からの話だった。日本に鉛筆が入って来たのは、1889年のパリ万博に派遣された日本人が製造法を持ち帰った時からだそうだ。日本で最初に鉛筆を使ったのは、徳川家康だった。その鉛筆は現存していて、日光東照宮にある。また世界で一番古い鉛筆を持った写真があるが、それはベートーベンである。社長の話は面白かった。
そしていよいよ工場見学になった。
隣の木造の建物の2階に上がると、ガラス越しに、現場が見える。
2つのラインがあり、作業員が2人だけだった。
鉛筆工場は昔から自動化が進んでいる業種で、その機械も70年ほど前のものを大事に使っているのだそうだ。部品もなく、いまでは自社で作るそうだ。
機械は作業員が調整中で、機械に詳しい私でなければなんだか分からないだろう。
それだけで工場見学は終わりで、次に事務所の隣にある鉛筆神社に行った。
日本で鉛筆神社はここだけである。この場所を購入した時に古い壊れかけた社があったので、近くの神社に相談に行き、了解を得て鉛筆神社を建立したのだそうだ。
(おまけの話)
呆気なく工場見学が終わり、また元の部屋に戻る。
ここからは社長の独壇場である。鉛筆業は、四つ木から始まった。
最初の頃は分業制で、板材製造、黒鉛の芯製造、鉛筆製造、塗装などに分れていて運搬のために荒川を利用したので、多くの工場が四つ木周辺に集まった。
北星鉛筆も創業時は板材製造だった。
鉛筆の生産の最盛期には、年間で14億本の鉛筆が作られた。それが現在では、7分の1の2億本となってしまった。社長の話はあちこちへ飛ぶ。
鉛筆はボールペンなど違い必ず書けるので、試し書きが不要なので選挙の投票に使われ続けている。鉛筆は六角形だが、色鉛筆は丸い。これは芯の硬さに関係がある。色鉛筆は削った状態で売っているのも、理由があった。
鉛筆製造では、50%くらいの切り屑が出る。昔はそれを風呂屋が引き取った。いまはただのゴミなので、それを生かすこと考えた。切り屑をさらに細かくし、粘着材と塗料を混ぜて絵の具にし他。それで絵を描き乾くと木になる。また社長の奥さんが、趣味で作った人形などが山ほど並べられていた。工場見学より、社長の話が面白かった。
\ この記事をシェアする /







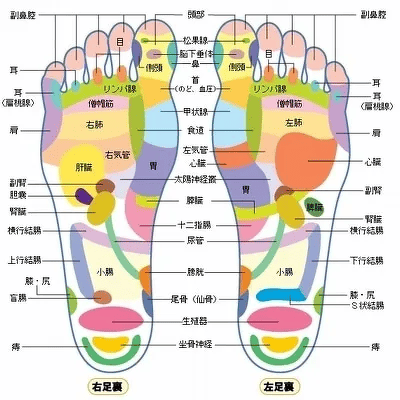











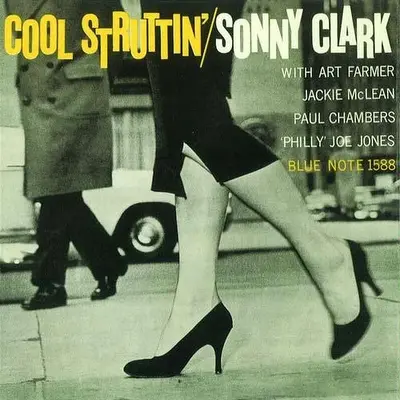
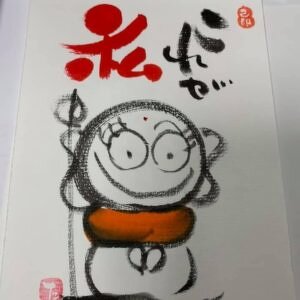













コメントはまだありません。
コメントを書く