都内の「3大鯉のぼり」の名所と言えば、東京タワー、東京スカイツリー、ミッドタウン六本木ではないかと私は考えている。そこで今回はその3ヶ所の鯉のぼりを、写真に撮って紹介しようと思う。
先ずは「東京スカイツリー」に行ってみた。都バスに乗れば、私の家の前から「亀戸行き」で「東京スカイツリー」の前まで連れて行ってくれる。その前に「鯉のぼり」の起源を調べてみた。
最近は年のせいか、あっさりとはならず、行く前に必ず歴史や起源を調べたくなる。
『江戸時代に将軍家に男の子が生まれると、旗指物や幟を立てて祝う習慣があった。やがてそれが武家に広がり、それが次に庶民に広がった。その後、庶民の間では幟の形を鯉にするようになった』。
「鯉のぼり」の鯉の3色にも、役割がある。
黑色は一家の大黒柱のお父さん、赤色はお母さん、青色が子供と決っている。
・・・とは言うものの、最近は紫色や緑色などもあり、伝統よりはデザイン優先となっている。
外付けエスカレーターに乗って、4階まで上がるが館内には入らない。
そこから「鯉のぼり」が始まる。
割合に小さめの「鯉のぼり」が、紐に吊るされている通路を進む。
見上げると東京スカイツリーの頂上が、やっと見える。
広場には「鯉のぼりがアチコチで泳いでいる」と言いたいが、風が無いので垂れ下がっている。
一番端まで行って、階段を1階まで降りる。
また見上げると、東京スカイツリーと鯉のぼりが上手く画面に入った。
横の道路の下には北十間川があり、そこに大量の「鯉のぼり」が並んでいた。
見渡す限りなので、500匹くらいはあるだろうか?
ここはあまり目立たないのか、観光客の姿も少なかった。
相変わらず風が吹かないので、鯉のぼりは垂れ下がっている。
風が吹くのを待っていたが、この時は遂に吹かなかった。
「東京スカイツリー」で写真を撮り終っても、まだ12時にもなっていなかった。
そこで地下鉄「都営・浅草線」で、1本で行ける「東京タワー」に向かった。
「大門駅」で降りて増上寺の中を通り抜けて、少し先が東京タワーである。
交差点を渡り、最後の急坂の登りがキツイ。
頭を上げると、東京タワーの足元に吊るされた鯉のぼりが見えて来る。
現地に着くと東京タワーの赤い鉄骨に吊るされた、大量の鯉のぼりが垂れ下がっている。例年と同じ光景で、あまり変わり映えしない。
大勢の観光客が来ていて、なんとか鯉のぼりと東京タワーを入れた写真を撮ろうと、しゃがんだり、地面にスマホを置いたりしている。
風が吹かないので、鯉のぼりは泳がない。鯉のぼりは泳いでいる姿が美しい。
泳がない鯉のぼりというものは、なんだか「だらしない」ように感じるのは私だけか?
しかも風が吹いた時に絡まった鯉のぼりがそのままなので、見た目が悪い。
外国人観光客はアジア人が多く、東京スカイツリーとは正反対だ。
私も東京タワーの方が、東京スカイツリーより好きである。
学生時代から見慣れているのが、その理由かもしれない。
(おまけの話)
1日目は東京スカイツリーと東京タワーで終った。
色々と野暮用があったので、少し経ってから「ミッドタウン六本木」に行った。
ミッドタウンの裏に、木立に囲まれた道路がある。
車道と歩道が木立で仕切られているので、安心して歩いて行ける。
私の行った時は、幼稚園の生徒達が「鯉のぼり」を見に来ていた。
「鯉のぼり」は木立の端から端まで、約200メートルの間に吊るされている。
ここの「鯉のぼり」は、デザインが素晴らしい。
伝統的な「鯉のぼり」は1匹もいなかった。
「風よ吹いてくれ」と願ったが、建物が邪魔をして風が通らないようだ。
デザインに同じものは無いようで、そのデザインを見るだけでも楽しい。
終りの方の大通りに近くなったところで、風が吹いて来た。
「鯉のぼり」が泳いだ! 腹いっぱいに風を受け、丸々と太った鯉になった。
やはり「鯉のぼりは、こうでなくちゃ!」と感じて、3ヵ所の鯉のぼり見物は最後を飾って終ったのである。
\ この記事をシェアする /







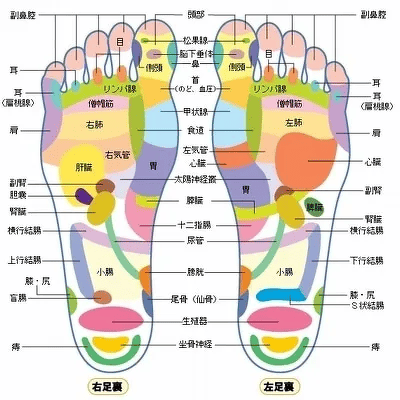











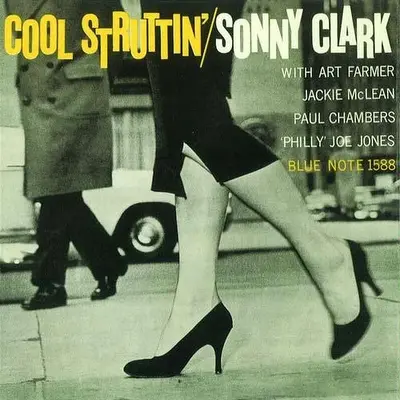
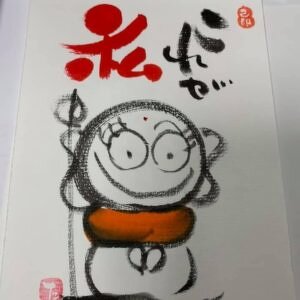













コメントはまだありません。
コメントを書く