こんにちは☼
昨日は
二十四節気(にじゅうしせっき)の最後、
「大寒」❄️で、冬の最も寒い時期に当たる頃。
だけど、暖かな一日でしたよね。
二十四節気とは陰暦でいう季節の区分。
一年を春夏秋冬の4つの季節に分け、
それを更に6つに分けて、
季節を表わす名前を付けたものなんです。
大寒の前の「小寒(しょうかん)」は
寒の入りと言われ、
厳しい寒さが始まる頃、とされています。
そして「大寒」の期間は
1月20日から、
「立春(りっしゅん)」の前日である
2月2日の節分までを言います。
陰陽太極図でも分かるように、
「陽」の気が増えてきて、
春に近づいているのが分かりますね。
暖かいと言ってもまだ1月。
春に向かい、春に備えて、
気力や体力を温存しておくのが大事です。☝️
薬膳では
春になって体調良く過ごす為には、
冬の今こそ、
体を整えておく事が必要と考えます。
食べ物もそうですが、
直ぐ出来る事は、体から熱を奪わない事。
体が冷えると、表面だけでなく
内臓も冷えて気血の巡りが悪くなります。←不調の原因
特に、
寒さを嫌う「腎」の働きが弱くなりがち。
(←「腎臓」そのものではないです)
これは、
体を温める働きをする「腎」が冷えると膀胱も冷える
↓
冷えで尿をためる膀胱の機能も低下しトイレの回数が増える
↓
それでも腎や膀胱が頑張って働く💦ので弱る
腎はホルモンの分泌中心に、成長・老化など、
人体のエネルギーの源としての働きに関わっている、
と考えられているので、腎が弱ると、
気力・体力も消耗して免疫力や抵抗力が弱ります。🙀
それで、冬には
「腎」を補ってあげる食材が良い、という訳です。
例えば、
黒ごま、黒糖、黒豆、黒米、
海藻類、黒きくらげ、ヒジキなどの「黒い食材」。
生姜、人参、にんにく、にら、
ねぎ、かぼちゃなどの「体を温める食材」。
あさり、イカ、いわし、たら、ほたて、
しじみ、なまこ、海藻などの「鹹味(かんみ)のある食材」。
※鹹味は塩辛いものなので摂り過ぎ注意☢️
だから、昔からの漬物は、
鹹味で冬の食材として理に適っているんだね。
生野菜よりも、根菜類の煮物や
葉野菜の温野菜が体を温め、体の熱を逃がしません。
長くなりましたが、(;^ω^)
重ね着などの工夫をしながら、
暖かい環境でお過ごし下さいませ~。
この記事が気に入ってくれたら
最後にいいね!で応援してね!
\ この記事をシェアする /







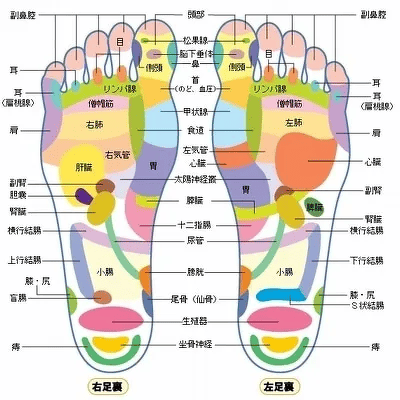











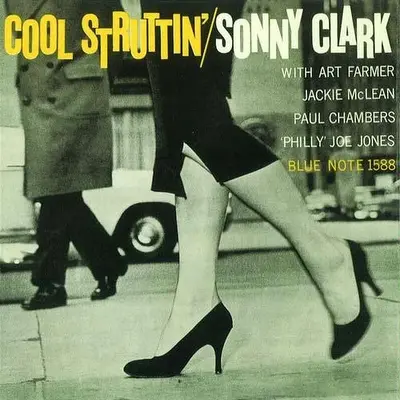
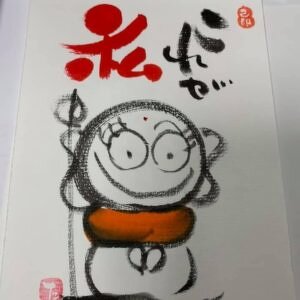





コメントはまだありません。
コメントを書く