弟から父が危篤となったことを知らされ、
僕は喪服を用意して横浜に向かった。
父がこうして亡くなっていくということは
僕にとってそれほど悲しい出来事ではなかった。
それがなぜだかはわからない。
子どもの頃はとても可愛がってくれて
将来を思ってくれて
大切に育ててくれていたはずなのに
そして僕自身も親になって
親の気持ちが痛いほどわかるようになった
そのはずだったのに
僕の心は意外にもクールだった。
それは多分、
弟も同じだったに違いない。
あいつも電話口で至って冷静であったから。
しかし、弟は僕よりも父に似ていた。
短気な性格やこだわりの強いところとか。
父も弟を自分に似ていると思っていたようだ。
だから余計に厳しく育ててしまったのかも
しれない。
そして二人とも同じように肺がんとなった。
弟が横浜に来てからは、
弟は父と同じ病院に通い、
同じ担当医に医療措置をしてもらっていたのだ。
父が入院しているときに、
弟が検査入院し、
親子で同じフロアにいたことがある。
その際には看護師の間でも
結構有名な親子になっていたらしい。
さて、
弟から連絡を受けて翌日早朝の飛行機で
僕は横浜に向かったわけだが、
僕が病院に着いた時に、親父はケロッとした顔で
ベッドで横になって起きていた。
そして「なんだ。お前、来たのか。」
なんて言ってきた。
僕はというと、やはりうれしかった。
諦めてはいたものの、
こうしてまた会話できるのは
やはりうれしいことなのか。
少し会話しても昨晩のことは全く
覚えていないという。
しかし戦争の焼け野原を経験した世代は
やはりただでは死なないようだ。
実にたくましく生きている。
だが、声はやっと出せるくらいの弱々しさ。
医者の話によると
今回の熱によって嚥下機能もやられたため、
このあとは胃瘻などの延命措置をしないと
もうダメでしょうと言われた。
人間は普通の点滴だけでは
やはり延命はできないということを
初めて知った。
やるなら食道から栄養を流し込むか、
太い静脈に穴をあけてか
ということになるわけだ。
しかしもちろんあの親父だ。
「このあとのわずかな命、
食いたいものを食えないよりも
食いたものを食って死んだほうがいい」
と強く希望した。
医者も「確かにそういう考えもありますね」と
一度はそう言ってくれたのだが、
病院としてはそうもいかないとのことになり、
結局父は酒もたばこも自由にのめるような
そんなホスピスに移り
好きなものを食う生活となった。
そして1ヶ月ほど経ち、
北海道に戻っていた僕に
弟から早朝に連絡があった。
「親父が死んだ。」
(つづく)
\ この記事をシェアする /







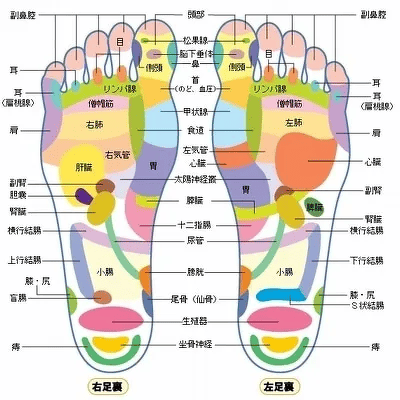

















コメントはまだありません。
コメントを書く