人はなぜ「学びたい」という衝動に駆られるのだろうか。おそらく生存のために必要であったがゆえに、進化の過程で学習本能というものが組み込まれたのだと考えられる。学者たちもそのように結論づけているはずである(確認はしていないが)。これが「人間には向上心がある」という命題の根拠となっているのだろう。
学生時代、俺は勉強というものが嫌いだった。心底嫌いだった。幼稚園受験から始まり受験戦争に至るまで、俺にとって勉強はテストで点数を取るための単なる道具に過ぎなかった。それ以上でも以下でもなかった。加えて周囲には小学校から大学まで、常に優秀な友人ばかりがおり、いつも「自分は頭が悪い」という劣等感を抱かされていた。言い訳になるかもしれないが、それが嫌いになった理由だと思う。
しかし本来「学び」とは違うのである。
「学ぶ」とは「知る」こと、「発見」することである。好奇心を持っているならば、知らなかったことを知ることは本来「喜び」となるはずだ。なぜなら、それは人間が求める「刺激」そのものだからである。さらに知識が増えると、自分が少し強くなったような感覚を覚える。知識は「安心」ももたらしてくれるのである。テストのための勉強という視点ではなく、自分の世界を広げ好奇心を満たすという視点で捉えれば、勉強は知的な冒険となる。何歳になっても楽しめるはずなのだ。になってもそれは楽しいものであるはずだ。
好奇心を満たして楽しむだけであれば、それで良いだろう。しかし知識を用いて何かをアウトプットするということになると、状況は変わってくる。もはや記憶しておく必要性は減少している。スマートフォンで記憶よりも正確な情報が瞬時に得られるからである。アウトプットの「手段」としての学びは、もはや不要になりつつある。
「いやいや・・・知識を自分のものとし、それを基に良いアウトプットするためにはインプットするできるだけ多くの知識が必要ではないか」という意見もあるだろう。しかしAIが急速に進化し、人間よりもはるかに正確にアウトプットできる現在、個人が大量の知識を蓄積する時代は終わったと言わざるを得ない。多くの本を読んでいなくとも、AIが過去の賢人たちの知恵を集積し分析し、細かな要望にも応じてカスタマイズしたアウトプットを提供してくれるのである。
そうなると、人間にとって思考が果たす役割とは何なのだろうか。どう考えても、思考は自分の内面における自己満足の旅の手段に留まるのではないだろうか。
そういうわけで、最近何十年かぶりに再開した英語の勉強も、何か空虚なものに感じられてきた。

\ この記事をシェアする /







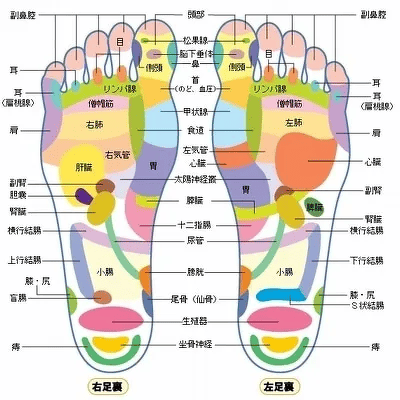











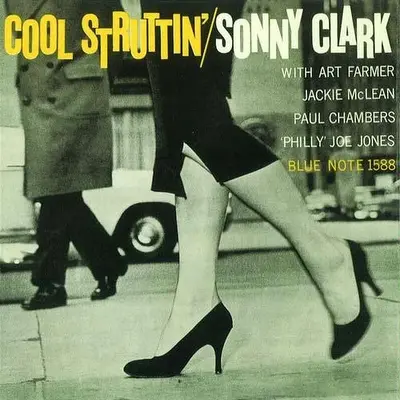
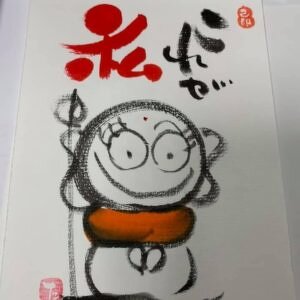



友人に誘われて初めてブログを拝読させていただきました。
私が参加しているPC塾でAIによる検索授業が始まりました。
Geminiを使っていろいろと質問を繰り返していて、気付いたことはこれは「作業」である。決して「知識の追求」ではない。なにも考えずに質問を繰り返していて、自分の思考経路を経る事く「答」が繰り出されてきました。今日のブログに納得してのコメントを送りました。
こんにちは!どうもありがとうございます。考えてみると私が若い頃はまだPCも普及したての頃。あの頃はPCが仕事に欠かせないものになるとは全く想像ができませんでしたが、それがいつのまにかなくてはならないものになった。携帯電話やスマホもその通りで、つまり人間は慣れてしまうとそれが当たり前になるから恐ろしい。一方で昔を忘れられる素晴らしい適応力があるともいえましょう。人間の能力がこの何百年間で失った部分も多いのでしょうが、得たものもたくさんあるのかもしれません。そう考えるといつの時代も人間はその適応力を持って生き続けることができるのか?そう願ってやみません。