東京駅に行く時は、時間がある限り「丸の内仲通り」の様子を見に行く。
たまには面白そうなイベントに出会えるからだ。
9月初旬に行ってみたら、「MARUNOUCHI STREET PARK SUMMER」というイベントが行われていた。
特に派手な動きがあるイベントではなく、道路に人工芝を敷き詰めて寛ぎの空間を作ってあった。昼前なのでまだサラリーマン達は来ていないので、静かな場所になっていた。

HPによると『このイベントは2019年から実施している。道路などの公共空間において24時間の交通規制を実施し、歩行者空間を創出して来た。今回は景観と機能を調和・融合させる「Blending the Streetscape」をコンセプトに、丸の内仲通り沿道飲食施設との連携による店舗と道路、ボラード撤去による歩車道のシームレス化に加え、テーブルやベンチ、ファニチャー、芝生や植栽プランターの設置による、緑と道路を一体的に繋げる景観づくりを意識した』と書いてある。
しかし英語が多くて、私にはよく分からない。
丸の内で働く人エリート・サラリーマンが考えそうな文章である。

人工芝の道路を歩いて行くと、両側のところどころに新しいアートが出現していた。
下の写真の作品「Matching Thoughts」は解説を読むと『アンリ・シャギャーンとピエール・シャギャーンが2004年にウィーンで制作した2枚の絵をもとに造られた立体作品である。当時の作品をベースに、単にビジュアルが目立つだけでないものを目指した。・・・』
『現代アートとしてはマテリアルも古く、革新的な造形ではないが、ディテールやそのなかに潜むエスプリに、2人が持っている近代彫刻へのリスペクトをどれくらい込められるかが課題であり、この2体の彫刻に反映させている。それらを表現するための作品素材として、扱いづらいモルタルを用い、その素材の変化する様も楽しみセッションを重ねた作品制作の中には、互いへの信頼や共鳴がうかがえる』。

次のアート 「Whirling Journey」はなんだか面白い。
これも解説によると『頭の中でぐるぐるとめぐる思考や空想、そしてその先に、少しずつ立ち上がる希望。内と外、都市と自然、想像と現実のあいだをめぐりながら、 揺らぎつつも確かに進んでいく心の旅路のようなイメージを込めました。自分の内側から生まれる新しい存在と、それを育む過程をかたちにした作品です。大きな顔をぬっと現してみたいと思いました。・・・』
『そして、屋外展示に耐えられるようにするため、ブロンズに置き換えて制作していますが、もともとは一本の大きな木から生まれている、ということが、より伝わるような作品にしたいと思い、 原型となる楠木ととことん向き合いながら、あまり明確な完成系のイメージをつくらず、形を決めていきました』。

「私は街を飛ぶ」は私には作品の題名との関係がよく分からない。
解説では『その清楚な佇まいで行き交う人々の関心を惹き付けずにはおかない。気づいてみればハッとするほどの美しい人が、すっとした顔をしてそこにいる。大理石の目を嵌め込んだ木彫のお洒落な像である。少し垂れた目で、心なしか遠くを見遣っている。思いの外の無表情。・・・』
『だがわざとつくった身分証明書のごとき無表情ではない。鼻筋が通っていて、いわば丸の内仲通りを飛ぶように行き来する理性派の女性かもしれない。なにかの欲望にとりつかれ、ギラついたところなど微塵もない。ところどころ赤く彩色されながらも、結局は素顔そのものといっていいだろう』。

次の「眠りながら語り、歌う」はタイトルが凄い。
人は眠りながら語ったり、歌ったりしたら「寝惚けか」、「認知症」を疑われる。
解説では『地底には無数の生命が存在し、そして数十億年の営みの歴史が刻まれています。忘れられて行く、無名で無数の物と事。そして思いや願い。地底という場所は全てが溶け込み、混在している世界のように感じます。地底には無数の生命が存在し、そして数十億年の営みの歴史が刻まれています。・・・』
『忘れられていく、無名で無数の物と事。そして思いや願い。地底という場所は、全てが溶け込み、混在している世界のように感じます。 地底と大地と空を繋げるものが樹木であり、イメージはそこを通って生成されています。様々なものが戯れ、集積され、茸のように少しずつ形が現れていきます。それはあたかも地底のサーカス、地底王国の宴のようといえるかもしれません』。

次々とアートが登場するので、『次のアートはなんだろう?』と思うようになる。
そこへ現れたのが、私の理解を超えるアートだった。
単なる切り株のように見えるが「なんだろう?」と思い、作品名と作者が書かれたプレートを探した。しかし普通は作品の下に置かれているプレートが無いのである。
そして落ち着いて、周りをよく見た。すると仲通りの並木の中の1本だと気が付いた。
これはアートではなく、なにかの理由で危険なので切られた木であった。
奇抜なアートを見続けると、切り株さえもアートに見えるようになる。

(おまけの話)【新東京ビルのアート】
丸の内仲通りを有楽町方面に進み、大きな道路を渡ると左側に「新東京ビル」がある。
正式名は「新東京ビルヂング」で、今では「新」と「ビルヂング」が少し恥ずかしい古いビルである。このビルの2階には写真のギャラリーがあり、私は時々、そこに見に行っている。正面入口から中に入ると、素晴らしい昔風の景観に出会える。
天井のデザインが私は好きだ。2階までが吹き抜けなので、その向こうにギャラリーが見える。そのギャラリーの壁際には長椅子が連なっていて、休憩するにはちょうど良い。
いずれ高層ビルに建て替えられる時が来るのだろうが、私はこのまま残して欲しい気持ちだ。

9月の作品展は「海神の咆哮」(わだつみのほうこう)だった。
作品の解説は『天が裂け、風が叫ぶ。黒き雲が空を裂き、蒼の底から巨大なうねりが姿を現す。それは遠い神話の時代から、誰にも抗えぬ律動をまとい、怒りとともに地平を揺るがす。海は牙をむき、叫びをあげ、白き奔流となって岩を打ち砕く。・・・』
『沈黙は喰われ、祈りは吹き飛ばされ、ただ咆哮だけが空を満たす。それは破壊か、それとも浄化か。あまりに純粋で、あまりに容赦のない力。すべての生が試される瞬間に、人は言葉を失い、ただその場に立つ。目を見開いたまま、心の奥底で、この咆哮が自らのなかの何かを震わせるのを感じながら』とあった。私は作品の写真より、この文章に感動した。

エレベーターで1階に降りて左側の出口に向かった。
その通路の左側のガラスケースの中にもアートがあった。
このビルはアートに力を入れているようだ。
ガラスケースの中には「仮囲い」のアート作品の作品集が並んでいた。
そのガラスには『YUURYAKUCHO ARTLIGHT PROJRCTは、仮囲いやファザードを舞台に、都市とアートに新たな交わりを生み出すことを目的としたプロジェクト。アーチストによるリサーチを通じて制作された作品を街なかにインストールすることによって、都市に多様な視点や思想をもたらし、街ゆくひとびとと作品の間にコミュニケーションが生まれることを目指している』と書いてあった。
最近はアチコチで工事現場の仮囲いのアートを見るようになり、私はとても楽しみにしている。

\ この記事をシェアする /

北海道伊達市に2003年夏より毎年季節移住に来ていた東京出身のH氏。夏の間の3ヵ月間をトーヤレイクヒルG.C.のコテージに滞在していたが、ゴルフ場の閉鎖で滞在先を失う。それ以降は行く先が無く、都心で徘徊の毎日。
- アクセス総数
- 1,557,689回






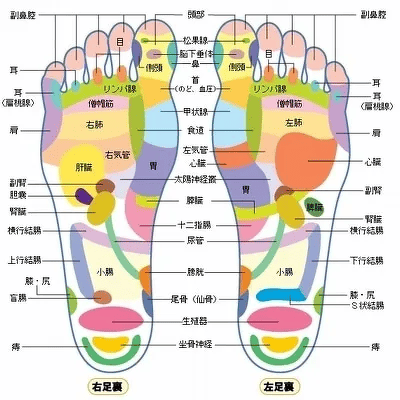











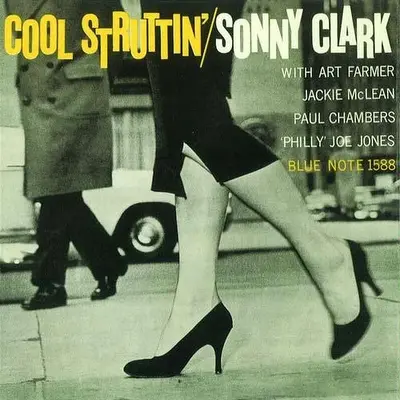
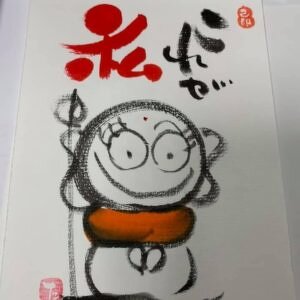



丸の内通りのアートへの説明文の英語表記の多い事。日本人は文章の中に英語を含めるとその文章が偉く?見えると考えるみたいだ!
只々難解にして一般の人には???と思わせるためなんだろう。コメント欄で外国に住み、そこで生活を長くされているシンジさんの文章にほとんど外国語が入っていないのはわかり易さを心掛けている教養人の文だからと思う。
Yさま、
お褒めいただき、恐縮です。 いつも読んでくださっているようで、ありがとうございます。
日本語の中に突然現れる外国語には、辟易とさせられます。
また、造語で多いのですが、特に新しいビルや場所に、英語とフランス語やイタリア語を混ぜて使っている例が多いのや、駄洒落ふうに発音をもじった語なども、見ていて(聞いていて)、これらはなんて幼い発想なのだろう、と恥ずかしくなります。
丸の内仲通りのアートの説明文です。こういうインテリぶった文章を書いて提出していた、”ツッパッテいた”私の大学1-2年の頃を思い出させます。
アートに説明は不必要で、作品を見たものが自由に感じ取れば、それでいいはずです。たとえば、17文字の俳句に説明はなく、読者がイメージを勝手に広げればそれでいいので、解釈は読者の数だけある、というのが私の信条です。