■元伊勢
日本には8万社を超えるメチャクチャ多い数の神社がありますが、その中の頂点と言ったら三重県伊勢市にある伊勢神宮ですよね…。伊勢神宮は正式な名称は「神宮」と言うのを知っていますかね?唯一無二の存在だから、頭に名称をつける必要がないからだそうで…。神域も広く、皇大神宮(内宮)と豊受大神宮(外宮)はおよそ5キロも離れている。このうち内宮には、天皇家の祖先神・天照大神が、外宮には、五穀豊穣の神・豊受大神が祀られている…。
天皇家からの崇敬も篤く、現在の皇太子徳仁親王も式年遷宮に向けた伊勢神宮の行事に参列するなど、しばしば伊勢神宮に参拝している。また、宮中で祈年祭や神嘗祭、新嘗祭等が行われる時には伊勢神宮でも同じ祭祀が行われ、その時には伊勢神宮に天皇家から勅使が遣わされる。まぁ、儀式は完全に共有されている訳ですね…。
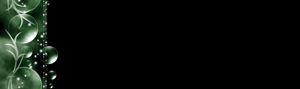
まず、第10代天皇である崇神天皇5年(紀元前93年?)に全国で疫病が流行した…この時死者は人口の半分を突破し、農民の逃亡が相次いだ…。
この頃にはまだ、天照大神は宮中に祀られていた…。ところが倭大国魂という極めて神威の強い神と一緒だったので、互いの神が互いの力を怖れあい、同じ場所に住む事は我慢が出来なくなったらしいの…。疫病の流行もそれが原因だったようで…そこで崇神天皇は豊鍬入姫を巫女として、天照大神を倭(大和)の笠縫邑(現・奈良県三輪市)に祀るように命じる。
そこから豊鍬入姫は、鎮座するに最適な土地を求め、各地を転々と移動し始めた!旅は彼女だけでは終わらず、次の垂仁天皇の時代になると倭姫に引き継がれて、結局、現在の伊勢の地に至るまでに、旅は90年ほどかかった。経由した土地(神社)だけでも、分かっているだけで20カ所以上もあって、この時、一時的であれ天照大神が祀られた伝承を持つ神社や場所は「元伊勢」と呼ばれているのさ…。
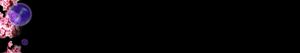
神話的な説明を抜きにしても、何故このように天照大神が諸国を巡らなければならなかったのか?という事は、実は今でもよく分かってはおらず、征服者による侵攻ルートの可能性や、古代王朝の移動跡と考える事も出来はするけど、それにしてはあまりにもルートが細かすぎる…。あるいは、元伊勢と呼ばれる場所を比較しても、なかなか共通店が発見出来ない…。

「1人では食事も安らかにままならないので、丹波国の真名井にいる等由気大神を連れて来なさい」
この等由気大神=豊受大御神は、天照大神の大御饌(食物)を守護する神様な訳で…なお、伊勢神宮を参拝する時には、まず外宮に参り、その後で内宮をお参りするというのが正式で、これを「外宮先祭」という…。
